【単行本/ミステリ】
ジョン・ディクスン・カー〈奇蹟を解く男〉
D・G・グリーン
クイーン談話室
E・クイーン
ミステリー倶楽部へ行こう
山口雅也
本格ミステリの現在
笠井潔編
ショパンに飽きたら、ミステリー
青柳いづみこ

|
不可能な夢を追い続けた偉大なミステリ作家の生涯
|
|
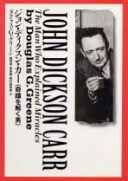 ジョン・ディクスン・カー〈奇蹟を解く男〉 ジョン・ディクスン・カー〈奇蹟を解く男〉
John Dickson Carr:The Man Who Explained Miracles (1995)
ダグラス・G・グリーン
森英俊・高田朔・西村真裕美訳
国書刊行会
◆A5判・上製ジャケット装・600頁
◆装丁=坂川栄治(坂川事務所)
1996年11月刊 3689円(税別) 品切 [amazon]
密室殺人、人間消失、見えない凶器など、強烈な謎の魅力と巧みなストーリー・テリングで、ミステリ・ファンを魅了しつづけてきた〈不可能犯罪の巨匠〉ジョン・ディクスン・カー。早熟な少年時代、『夜歩く』
の鮮烈なデビューから、数々の名作を生んだイギリス時代、ラジオドラマでの活躍、英米両国のミステリ作家との交友、ドイル伝の執筆、歴史ミステリへの傾倒、晩年の試行錯誤にいたるまで、綿密な資料調査と関係者のインタビューによって追跡。偉大なミステリ作家の、小説以上に痛快な生涯を鮮やかに浮かび上がらせた初の本格的評伝。
|
【目次】
序文
1.ユニオンタウン
2.ヒル・スクールとハヴァフォード時代
3.パリとブルックリン・ハイツ――悪魔のようなバンコラン
4.幕間――ジョン・ディクスン・カーと探偵小説
5.イギリス、そしてサー・ヘンリー・メリヴェールの登場
6.フェル博士とサー・ヘンリー・メリヴェールのさらなる殺人事件
7.魔術
8.歴史の魅力、ディテクション・クラブ、合作
9.ミニチュアの殺人
10.大戦とラジオ・ミステリ
11.大戦と謎解きミステリ
12.ドラマ――舞台、ラジオ、そして人生
13.第2次大戦後とドイル伝
14.ママロネック
15.王政復古への傾倒、摂政時代の洒落者たち、シャーロッキアンとしての功績
16.ロンドンへの帰還
17.再びママロネックへ――そしてまたどこかへ
18.最後の放浪
19.グリーンヴィルの小春日和
20.葬送
付録1.1922年のジョン・D・カー3世、リアリズム作家を語る
2.ドロシー・L・セイヤーズのカー書評
3.「火刑法廷」の第三の真相?
4.ジョン・ディクスン・カーは――スパイ?
5.「もうひとりの麗しの女性」――カーの執筆されざる長篇
ジョン・ディクスン・カー書誌/原注/索引
|
|
20世紀末、この本格ミステリ・ルネッサンスの時代に必須のテキストが現れた。ディクスン・カーという唯一無比の巨匠の伝記と作品分析を通じて、我々はミステリの真の精神と豊饒な技術の歴史を知ることになるだろう。横溝正史から最近のニューウェイヴのミステリ作家達に至るまで、計り知れぬ影響を与え続けてきた巨匠の評伝が面白くなかろうはずがない。ただ一言、MUST!
山口雅也
|
◇知られざる巨匠たち
◇舞台裏
TOP |
EQMMの名編集者クイーンがその舞台裏を明かした
ミステリ・ファンのための50のリーフ |
|
 クイーン談話室 クイーン談話室
In the Queen’s Parlor (1957)
エラリー・クイーン 谷口年史訳
国書刊行会
◆四六変型・上製ジャケット装・308頁
◆装丁=妹尾浩也
1994年7月刊 2136円(税別)品切 [amazon]
探偵小説狂の進化の4段階、カーとロースンのアイディア交換秘話、作家のサインの値段、有名作家が選んだ究極の名作ベスト、世界最初の女性探偵、ペンネームの選び方、タイトルの解剖学、紳士探偵の性生活、名探偵のトレードマーク他、本格ミステリの第一人者にして名編集者エラリー・クイーンが披露する、ミステリをめぐるさまざまな話題、「エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン(EQMM)」
の興味津々の編集裏話を満載。該博な知識と軽妙な語り口で人気を博したミステリ・エッセイの名著。付録として、合作方法・代作問題など、クイーンの創作の秘密に迫る小伝を付す。
|
【目次】500ドルの時計を1ドルで/偉大なるOE理論/グーズベリー・レイ/著者より謹呈/殊勲章/途方もなく、奇妙な/そして文学では/クイーンの談話室にて/“経”と“済学”/クレイグランドのライスすべてを/心の紡ぎ車/5年間(クインウェニアム)/彼女は全くスフィンクスではない/紳士探偵の性生活/古いクルミの新しいシワ/理解の門口に立って/実在しない蠅を叩く/ペンネームの選び方/ころんで大失敗/強烈な好奇心に駆られて/思索者からてこ、そして催眠状態へ/探偵小説の本質/幽霊の住みついたアメリカ/無人島へ持っていく本/ユリウス・アフリカヌスの遠い叫び/人類への貢献/すべての登場人物が干首にされている/深夜の楽しみ/鞄から飛び出した猫/巡回探偵/植物誌と動物誌/犯罪の精華/心をとらえる/世界の底辺からの報告/誰が忘れるでしょうか/決して古くはならない/二つの打率・イギリスとアメリカ/正当な名前/タイトルの解剖学/境界線を越えて/ポーエティック・ランセンス/偉大さの本質/過ぎ去りし懐かしき昔のために/探偵は医者である/再び著者より謹呈/高度なシャーロック・ホームズ風洞察力、あるいは言葉のたわむれ/動作は機敏に/探偵小説はどのように生れるか/ペンギンの蔓延/跋
クイーン小伝(EQIII)/クイーン、雑誌、そして談話室(EQIII)/訳者あとがき
|
TOP
|
伝説の名コラム「プレイバック」、映画と原作の関係など
ミステリーの魅力を語り尽くしたエッセイ集 |
|
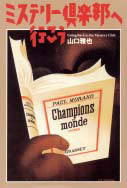 ミステリー倶楽部へ行こう ミステリー倶楽部へ行こう
山口雅也
国書刊行会
◆四六判・上製ジャケット装・374頁
◆装丁=坂川栄治(坂川事務所)
◆装画=カッサンドル
1996年1月刊 本体1942円 [amazon]
2001年7月 文庫化→講談社文庫 本体971円
埋もれた傑作から実現しなかった短編集まで、入手困難な幻の名作の数かずを紹介、多くのミステリー・ファンを古書店へと走らせた、作家デビュー前の伝説の名コラム「プレイバック」をはじめ、カー、クイーンら最愛の作家たちをめぐるエッセイ、ブランド、ジェイムズを尋ねる英国ミステリー紀行、007シリーズにみる奇妙な国ニッポン、初めて読んだミステリーの思い出、美食や子供をテーマにした架空のアンソロジー、ミステリー映画と原作の関係などなど、クラシックから現代ミステリー、モダンホラーまで、その多彩な魅力を語り尽くした、ミステリーの達人、山口雅也初のエッセイ集。
|
山口雅也 Yamaguchi Masaya
1954年、横須賀市生まれ。早稲田大学法学部卒業。ミステリ・映画・音楽などの評論活動から、1889年、『生ける屍の死』
で作家デビュー。以後、『キッド・ピストルズの冒涜』
『13人目の探偵士』 『キッド・ピストルズの妄想』
『ミステリーズ』 『日本殺人事件』 『キッド・ピストルズの慢心』『マニアックス』
『続日本殺人事件』 と、つねに新しい本格の可能性を模索しつづけ、日本ミステリ界に独自の地位を築く。
エッセイ集には他に、音楽に関する文章を集めた本書の姉妹篇ともいうべき
『ミステリーDISCを聴こう』 (メディアファクトリー)、マザーグースとミステリをテーマにした
『マザーグースは殺人鵞鳥』 (原書房) がある。山口ファンはこちらも要チェック。
|
|
コンビニエンス・ストアに並ぶカップ麺程度の
「現実」 を売り物にするミステリーは欲しくない。逢いたいのは、レジ・カウンターの奥の倉庫に夜な夜な現われる亡霊だ。……彼は革ジャンで決め、ミュージック・カセットをガンガン鳴らし、いつもへらへら笑っている。ちょっと気のふれた亡霊なのだ。そいつは、めったに店頭には並ばない缶詰の棚の前で、自分の気に入った商品を守りつづけている。
(「ミステリーの亡霊に」 より) |
◇舞台裏
TOP
|
日本ミステリ 本格ルネッサンス!!
綾辻行人から京極夏彦まで、90年代ミステリ・シーンを検証 |
|
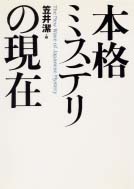 本格ミステリの現在 本格ミステリの現在
笠井潔=編
国書刊行会
◆四六変型・上製ジャケット装・490頁
◆装丁=坂川栄治(坂川事務所)
1997年9月刊 3000円(税別) [amazon]
日本推理作家協会賞受賞
1987年、綾辻行人 『十角館の殺人』 の刊行を皮切りに、本格派を標榜する特異な才能が次々に出現、さまざまな論議を呼びながら、それぞれの方法でミステリの歴史に新たな地平を切り拓いてきた。島田荘司、竹本健治、綾辻行人、法月綸太郎、北村薫、山口雅也、宮部みゆき、京極夏彦など、現代日本ミステリを代表する作家16人の作品世界を解読、〈新本格〉登場から10年、本格ルネッサンスを迎えた日本ミステリの現在を検証する、ミステリ批評の新しい冒険。
|
【目次】
まえがき●探偵小説の地層学 笠井潔
竹本健治論●尾を喰う蛇[ウロボロス]は〈絶対〉を夢見る 千街晶之
笠井潔論●大量死と密室
法月綸太郎
島田荘司論●挑発する皮膚
法月綸太郎
東野圭吾論●愛があるから鞭打つのか
北村薫
綾辻行人論●館幻想
濤岡寿子
折原一論●決算後の風景 田中博
法月綸太郎論●「二」の悲劇 巽昌章
有栖川有栖論●楽園が罅割れるとき 千街晶之
宮部みゆき論●語りと灯
濤岡寿子
我孫子武丸論●メタ・ヒューマニズム序説
夏来健次
北村薫論●可憐なる巫女たちの物語 加納朋子
山口雅也論●パンキー・ファントムに柩はいらない 有栖川有栖
摩耶雄崇論●形式の大破局[カタストロフィ]
佳多山大地
井上夢人論●意識・身体・小説・現実 田中博
二階堂黎人論●怪人のいる風景
鷹城宏
京極夏彦論●フロイトの「古井戸」
武田信明
|
|
綾辻行人の登場から10年。多数の有力作家の輩出と力作、秀作の相次ぐ出現の結果、ようやく現代本格も独立した地層の観を呈してきたわけだが、このムーブメントはまた、創作以外に優れた批評作品を生み出しつつある点で、きわめて画期的である。本書は「野性時代」誌に連載された新進批評家による現代本格作家論を柱とし、それに書き下ろしの批評作品を加えて新たに編纂された。
島田荘司や竹本健治など現代の本格ムーブメントを準備した先行作家、さらに綾辻行人から京極夏彦にいたる現代本格の中心作家を、気鋭の批評家たちが縦横に論じた本書は、中島親の「斯界は永い間、『批評と評論』の刺激・警鐘の無い不自然な平穏の中に、惰眠を貪つて居たのだ」という警鐘にたいする、70年後の回答ともいえるだろう。本書の刊行が、日本のミステリ文学に犀利にして豊饒な批評精神をもたらす、大きな一歩となることを期待したい。
――笠井潔(「まえがき」より抜粋)
|
◇舞台裏
TOP |
ピアニストは不可能犯罪の夢を見るか?
音楽とミステリーの不思議な関係 |
|
 ショパンに飽きたら、ミステリー ショパンに飽きたら、ミステリー
青柳いづみこ
国書刊行会
◆四六判・上製ジャケット装・242頁
◆装丁=坂川栄治(坂川事務所)
◆装画=田谷純
1996年11月刊 1553円(税別) [amazon]
2000年11月 文庫化→創元ライブラリ
シャーロック・ホームズのヴァイオリンの腕前、「楽聖」
ベートーヴェンの探偵術、マザー・グースの不気味な魅力、ほとんどSM小説、ルブラン
「三十棺桶島」、「オペラ座の怪人」 の愛の声楽レッスン、ドビュッシーのオカルト世紀末etc。クリスティー、スタウト、ジャプリゾから横溝正史、赤川次郎、高村薫まで、熱烈なミステリー・ファンのピアニスト、青柳いづみこが解き明かす、音楽とミステリーの不思議な関係。
青柳いづみこ (あおやぎいづみこ)
ピアニスト、ドビュッシー研究家。フランス国立マルセイユ音楽院卒業。東京芸術大学博士課程終了。安川加壽子、ピエール・バルビゼに師事。全7回の〈ドビュッシー・シリーズ〉をはじめ、多くのリサイタルを開く。大阪音楽大学教授。CDに
『ドビュッシー・リサイタルI』 『雅なる宴』
『ドビュッシー・リサイタルII』、著書に 『ドビュッシー=想念のエクトプラズム』 (東京書籍)、『翼のはえた指
評伝安川加壽子』 (白水社)、『青柳瑞穂の生涯―真贋のあわいに』
(新潮社)がある。 |
TOP |