|
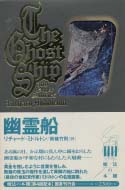 幽霊船 幽霊船
リチャード・ミドルトン 南條竹則訳
1997年4月刊 2300円[amazon] 品切
ある日突然、畑の真中に錨をおろした幽霊船と酔いどれ船長がひきおこす騒動を描いた抱腹絶倒の傑作「幽霊船」、永遠の彷徨をつづける孤独な幼い魂の叫びが胸を打つ幽霊譚「ブライトン街道で」をはじめ、黄金を惜しむように言葉を惜み、わずかな短篇と2冊の詩集を遺して、異郷の地に倒れた孤高の作家ミドルトンの名短篇集。
| 【収録作品】序(アーサー・マッケン)/幽霊船/ブライトン街道で/羊飼いの息子/棺桶屋/奇術師/逝けるエドワード/月の子たち/園生の鳥/誰か言ふべき/屋根の上の魚/小さな悲劇/詩人の寓話/ある本の物語/超人の伝記/高貴の血脈/警官の魂/幼い日のドラマ/新入生/大芸術家/雨降りの日/解題・ミドルトン小伝(南條竹則) |
|
リチャード・ミドルトン(1882-1911)
イギリスの作家。保険会社に勤めながら、詩や短篇を同人文芸誌に執筆。マッケン、サヴェージらと交遊をもつ。勤めを辞め文学活動に専念したが、次第に貧窮に陥り、1911年、ベルギー、ブリュッセルの下宿で服毒自殺。死後1週間後、雑誌社に送りつけていた 「幽霊船」 の原稿採用の通知が届いた。
|
この作家については、くだくだと贅言を費やすより、かつて
「ブライトン街道にて」 に付された平井呈一の解説を引用するのが一番だろう。
「彼は黄金 [きん] を惜しむようにことばを惜しんだ。(中略)
鬼才というのは、こういう人のことをいうのだ。もちろんミドルトンは二流
[マイナー] 作家である。十把ひとからげの文学史には名前も出ない、日蔭の作家である。わたしは二流作家を愛する。彼らには純粋の精神と情熱があるからである。わたしの好きなダウスンもクラッカンソープもマッケンもポウイスも、みな二流の作家である。ただ少数の人に発掘されて、その孤峭な才能を愛慕されるにすぎない。(中略)イギリスの文学史家S・M・エリスは、ミドルトンはもう10年早く生まれていたら、世紀末作家のなかに伍して、その才能を認められたろうといって嘆いているが、しょせんそれもこの小作家を愛するあまりの、運命に対する怨訴にすぎないだろう」
(創元推理文庫 『恐怖の愉しみ/上』 より)
TOP
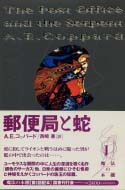 郵便局と蛇 郵便局と蛇
A・E・コッパード 西崎憲訳
1996年6月刊 2330円 [amazon] 品切
虎に扮してライオンと戦うはめになった男が、檻の中で出会ったのは……ユーモラスな展開の中に、運命の皮肉と人生の深淵を描いた
「銀色のサーカス」他、「辛子の野原」 「王女と太鼓」
「シオンへの道」 など、日常の裏側にひそむ神秘と怪奇を淡々とした筆致で物語るコッパードの詩情あふれる珠玉の短篇を収録。
| 【収録作品】銀色のサーカス/郵便局と蛇/うすのろサイモン/若く美しい柳/辛子の野原/ポリー・モーガン/王女と太鼓/幼子は迷いけり/シオンへの行進/A・E・コッパードについて(西崎憲) |
|
アルフレッド・エドガー・コッパード(1878-1957)
イギリスの作家・詩人。ケント州の港町に生まれ、早くに父親を亡くし、メッセンジャーボーイ、商店の店員、運送屋、工場の会計係などの職を転々とする。優れた短距離走選手でもあった。40歳近くなって短篇や詩の執筆をはじめ、やがてまとめられた作品集
『アダムとイヴとツネッテ』 (1921) で高い評価を受ける。生涯で20冊以上の作品集を遺した短篇の名手。
|
コッパーディアン、西崎憲氏による作者小伝は、まるでコッパード自身の小説のような味わい。本書収録作以外では、平井呈一訳編 『恐怖の愉しみ/上』 (創元推理文庫)収録の 「消えちゃった」 をおすすめしておきたい。フランス旅行中の一行が、ただひたすら、何の理由もなく、一人ずつ消えていくこの作品の、読後、気味の悪い空間にいきなり放りだされるような感覚は、ながく忘れることはできないだろう。
※新訳1篇を追加してちくま文庫より再刊。
TOP
 赤い館 赤い館
H・R・ウエイクフィールド
倉阪鬼一郎・鈴木克昌・西崎憲訳
1996年10月刊 2330円 [amazon] 品切
ラジオの生中継で入り込んだ幽霊屋敷に次々に出現する怪異と、凄惨きわまる結末――鬼気迫る恐怖譚
「ゴースト・ハント」、英語で書かれた最も怖い小説と世評の高い傑作
「赤い館」、実在の魔術師アレイスター・クロウリーをモデルに、呪術合戦をえがいた
「“彼の者現れて後去るべし”」 など、精妙な筆による恐怖の描出で、近代怪奇小説の頂点をきわめたウエイクフィールドの戦慄の物語集。
| 【収録作品】怪奇小説を書く理由/赤い館/ポーナル博士の見損じ/ゴースト・ハント/最初の一束/死の勝利/“彼の者現れて後去るべし”/悲哀の湖[うみ]/中心人物/不死鳥/さらば怪奇小説!/解説:最後のゴースト・ストーリイ作家(鈴木克昌) |
|
ハーバート・ラッセル・ウエイクフィールド(1888-1964)
イギリスの作家。オックスフォード大学卒業後、新聞社主の秘書、軍隊経験を経て、出版社に勤務。執筆に手を染める。怪奇小説集
『彼らは夕暮れに帰る』 『老人の顎鬚』 『棺の中の男』
『時計は12時を打つ』 他やミステリ長篇がある。抑制のきいた文体で簡潔に物語を展開し、最大限の恐怖効果を演出する、レ・ファニュ、M・R・ジェイムズとつづく英国怪奇小説の正統を受け継ぐ最後の作家。
|
伝統的なゴースト・ストーリーが、20世紀にはいって次第に洗練の度を増してきて、最後にたどりついたのがウエイクフィールドの怪奇短篇である。巻頭と巻末に2篇のエッセイを配したが、これは彼が怪奇小説を書く理由と、のちに、100篇もの怪奇短篇を書いてきた彼が、なぜ現代では怪奇小説が書きにくくなってしまったのか、を吐露した貴重な証言。
※本書収録の8篇に、「目隠し遊び」 「チャレルの谷」 「湿ったシーツ」 「ケルン」 「暗黒の場所」 など8篇を大幅増補して 『ゴースト・ハント』 (創元推理文庫 2012) を刊行。
TOP
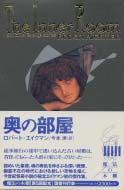 奥の部屋 奥の部屋
ロバート・エイクマン 今本渉訳
1997年9月刊 2300円 [amazon]
徒歩旅行の途中で迷い込んだ屋敷は昔遊んだ人形の家にそっくりだった。不気味な雰囲気に包まれた中篇
「奥の部屋」 他、「髪を束ねて」 「学友」
など、謎めいた象徴、魂の奥処をゆさぶる深い戦慄によって、幽霊不在の時代における新しい恐怖を描くエイクマンの本邦初の作品集。キング、ストラウブらが絶賛するモダンホラーの極北。
| 【収録作品】学友/髪を束ねて/待合室/恍惚/奥の部屋/訳者あとがき(今本渉) |
|
ロバート・エイクマン(1914-1981)
イギリスの作家。祖父に怪奇長篇 『黄金虫』
(1897) (創元推理文庫) を書いたリチャード・マーシュをもつ。運河の保存を目的とする内陸運河協会の設立に関わり、協会の秘書をしていたエリザベス・ジェイン・ハワードと共著のかたちで、作品集
We Are for the Dark (1951) を出版。1955年にシンシア・アスキスの怪奇小説アンソロジーに収められた
「鳴りひびく鐘の町」 は、このジャンルの名作として高い評価を得る。Dark
Entries(1964)を皮切りに、作品集を次々に刊行、そのstrangeな味わいの怪奇短篇は、キング、ストラウブら、モダンホラーの書き手たちにも衝撃をあたえた。
|
エイクマンのゴースト・ストーリーでは、もはや怪異ははっきりと目にみえる形では登場しない。しかし、何かが少しずつ狂っている、どこか腑に落ちない。そして、ひしひしと怖さが募ってくる。幽霊や妖怪が恐ろしいのではない。何かを怖いと感じる、恐怖感そのものを、エイクマンは執拗に描いていく。欧米でも、特に作家が好むタイプの作家だった。後期の作品では、さらにその作風は深まりをみせていく。ここからどこへ行くのかはわからないが、怪奇小説はここまで来てしまったのだ。
他に、中篇 「列車」 が 『怪奇小説の世紀3』 で読める。
初期の代表作「鳴りひびく鐘の町」は、R・ダール編 『ロナルド・ダールの幽霊物語』
(ハヤカワ・ミステリ文庫)で。あわせて 『看板描きと水晶の魚』 (筑摩書房)所収の「花よりもはかなく」 も。〈ミステリマガジン〉や 〈幻想と怪奇〉 に訳載された作品も、探して読む価値はある。
「このホラーが怖い'99」 第1位
TOP
 漁師とドラウグ 漁師とドラウグ
ヨナス・リー 中野善夫訳
1996年8月刊 2136円 [amazon]
挿絵=ローレンス・ハウスマン
買ったばかりの船に乗って帰途についたエリアスは、海魔ドラウグの操る船と出会った。募りゆく嵐のなか、乗り組んだ子供たちは一人また一人と波にさらわれていく……仮借なき海の恐怖を描く表題作をはじめ、ノルウエーの国民的作家が描く海の不思議と北の国の生活。フォークロア的想像力に満ち満ちた物語集。
| 【収録作品】漁師とドラウグ/スヨーホルメンのヨー/綱引き/岩の抽斗/アンドヴァルの鳥/イサクと牧師/風のトロル/妖魚/ラップ人の血/青い山脈の西で/「あたしだよ」/訳者あとがき(中野善夫) |
|
ヨナス・リー(1833-1908)
ノルウェーの作家。大学で法学を学び、卒業後、国の役所で働きながら、詩を書き始める。やがて手を出した木材業で失敗、文学活動に専念。第1作
『幻視者』 (1870) は大評判となり、やがてイプセン、ビョルンソン、ヒェランと共に、ノルウェー自然主義の4大作家と呼ばれる国民的作家となる。ノルウェーの民間伝承に取材、海の魔物や死人の王、妖術師などが登場する『トロル』(1891)も好評を博し、翌年、第2集も刊行された。本書は、1893年刊の英訳版
Weird Tales from Northern Seas from the Danish
of Jonas Lie を底本としている。
|
北欧の 『遠野物語』 ともいうべき奇譚集。しかし、単に民話を採集したものではなく、リーの筆によって文学的に再構成されている。
我々が親しんでいるグリムやベローの西欧の昔話とは、また一味違った魅力にあふれている。厳しい自然を反映してか、「漁師とドラウグ」
「岩の抽斗」 「綱引き」 など、思わずぞっとする結末の話も多い。訳者の中野善夫氏は、この本のために、ノルウェー語の勉強を始めてしまったというから脱帽である。
TOP
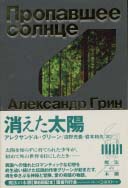 消えた太陽 消えた太陽
アレクサンドル・グリーン 沼野充義・岩本和久訳
1999年6月刊 2400円 [amazon]
太陽を知らずに育てられた少年が、初めて外の世界を目にしたとき……人間の夢見る力を謳いあげた
「消えた太陽」、他、革命の嵐吹き荒れるなか、異国への憧れとロマンティックな幻想を終生追い続け、ロシア中で愛読されてきた伝説的作家グリーンが紡ぎだす、神秘と冒険、愛の奇蹟の物語。
| 【収録作品】消えた太陽/犬通りの出来事/火と水/世界一周/おしゃべりな家の精/荒野の心/空の精/十四フィート/六本のマッチ/オーガスト・エズボーンの結婚/蛇/水彩画/森の泥棒/緑のランプ/冒険家/訳者あとがき:ズルバガンから来た夢想の騎士(沼野充義) |
|
アレクサンドル・グリーン(1880-1932)
ロシアの作家。子供の頃から欧米の冒険小説を読みふけり、外国への憧れを募らせ、10代で家を出て水夫となる。以後、漁師、金鉱探し、軍隊と職を替え、革命運動に共鳴、入獄と脱獄を繰り返し、放浪生活を続けるあいだに小説を書き始める。やがて
『深紅の帆』 『輝く世界』 などのロマンティックな幻想的作品を次々に発表、人気作家となった。死後、社会主義体制下のソ連にあって、彼の作品は追放の憂き目にあったが、〈雪解け〉
後、劇的な復活をとげ、以後、多くの読者に愛され続けている。
|
〈ここではないどこかへ〉という憧憬を生涯もちつづけた作家グリーンの代表的長篇は、これまでにも紹介されてきた。しかし、まとまった短篇集はこれが初めてである。グリーンの作品にも、悪や欺瞞、挫折や孤独が登場する。しかし、彼の〈夢見る力〉によせる揺るぎない信頼は、僕たちに勇気を与えてくれる。
他の邦訳作品をあげておく。
『深紅の帆』 フレア文庫
『波の上を駆ける女』 晶文社
『輝く世界』 沖積舎
『黄金の鎖』 ハヤカワ文庫FT(絶版)
他に短篇 「魔のレコード」が、『ロシア怪談集』 (河出文庫) で読める。
「SFが読みたい2000」 ベストSF 第18位
TOP
|