|
【内容見本でみる国書刊行会 第7回】
初期の海外文学部門から、英米文学の二巨人のコレクション。
《メルヴィル全集》 全12巻 (1981-83)
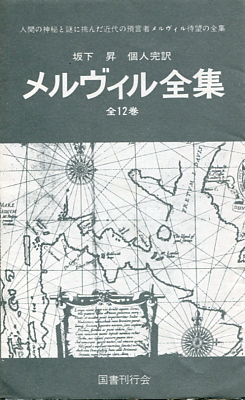
名作 『白鯨』 をはじめ、『タイピー』 『オムー』 の南洋物、寓意的な海洋ロマンス 『マーディ』 から近年再評価著しい 『ピエール』 『信用詐欺師』
まで、アメリカ・ルネサンスの巨人ハーマン・メルヴィルの長篇を坂下昇個人全訳で刊行。《ゴシック叢書》 収録の短篇集 『乙女たちの地獄』 とあわせれば、メルヴィルのほぼ全作品を国書刊行会版で読めてしまう。(叙事詩
『クラレル』 など若干の例外あり)
推薦文は大橋健三郎、中村真一郎、澁澤龍彦、田宮虎彦の各氏。
「メルヴィルは百年以上も前に近代の運命を感じ取り、それを乗り越えようとして結局それに殉じなければならなかったのだ」 (大橋健三郎)
「彼によって小説は、人間と絶対者との対話の場となった」(中村真一郎)
のちに坂下氏は 《Melville's Keywords》 (1989) という英文の大著も国書刊行会から刊行している。
《ヘンリー・ジェイムズ作品集》 全8巻 (1983-85)。監修=工藤好美
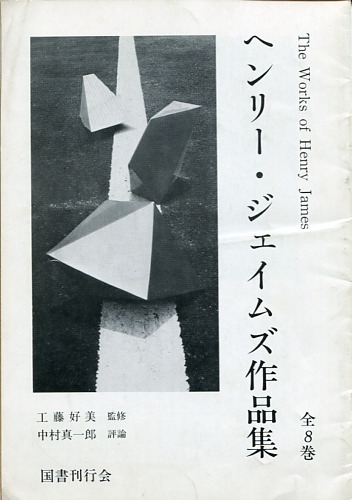
難解で知られるヘンリー・ジェイムズの 『鳩の翼』 『使者たち』 『黄金の盃』 等の大作を一挙翻訳紹介したコレクション。全16頁の小冊子。推薦文は篠田一士、澁澤龍彦、辻邦生、吉田秀和、大橋健三郎と、こちらも錚々たる顔触れ。各巻内容に略年譜も収載。
「彼はルネサンスの画家のように、遠近法によって世界を眺めるという技法を、徹頭徹尾、小説の構築のために応用して新生面を切りひらいた作家なのである」
(澁澤龍彦)
「ジェイムズもかなり小説好きの成熟した読者を要求する。その点、小説技巧的にも、ロマネスクの感覚においても、文明批評、人生批評においても、ジェイムズは第一級の作家である」
(辻邦生)
《世界幻想文学大系》 《ドラキュラ叢書》 《ゴシック叢書》 《セリーヌの作品》 と続くシリーズで、「訳のわからない社名の会社が訳の分からない本を出しやがって」
的な目でともすれば見られがちだった国書刊行会が、これなら文句あるまい(?)、とばかりに送りだした正統派の文学叢書。(しかし、世間の目はあまり変わらなかったような気も。結局、何を出しても
「国書さんらしいねェ……」 と取次や書店の担当者に言われてしまうのであった)
第6回< 目次 >第8回

|