| 函館市中の時代へ トップ | ||||||
| 私 の 思 い 出 の 東 高 | ||||||
| ☆東高校門は東高のシンボル☆ | ||||||
 ☆東高校門は東高のシンボル☆ ☆東高校門は東高のシンボル☆この度、講演をお引き受けするということで東高校に本当に何年かぶりでお伺いしました。 校舎はすっかり変わってきれいになりました。しかし変わらないもの、これは私の代から同じ状態で、これは東高過去のシンボルであるし現在のシンボルでもあり、おそらく未来に向けてのシンボルになっていくだろうなあという思いをした所がございます。 あなた方はおそらく気が付かないで毎日学校へ通っていると思いますけれど、それはあの門です。門柱があそこにありますね。この門、幅幅広い道路の両端にあまり目立つない門柱があります。私の時もああいう形でした。今もああいう形ですね。 なぜそなんことをふっと思い出したかというと―なぜそういうことを言うんだろうと思いになる方がいらっしゃるでしょうけれども―神戸で門の扉を閉めて生徒が亡くなるという事件がありましたね。  函館東高なら扉がないんだから幾ら先生が怒ってあそこでどなったって扉を閉めるわけにいかない門ですね。永久にあれは閉じない門であると、そしてあの門が東高を象徴するなあと思います。あれは自由の象徴ですね。そしてまた一方で、自由に伴って責任というものを示す、あれは2本の柱ではないかなあと思います。 函館東高なら扉がないんだから幾ら先生が怒ってあそこでどなったって扉を閉めるわけにいかない門ですね。永久にあれは閉じない門であると、そしてあの門が東高を象徴するなあと思います。あれは自由の象徴ですね。そしてまた一方で、自由に伴って責任というものを示す、あれは2本の柱ではないかなあと思います。あの門は東高は大事に大事にして、これからもあの形を保存していただきたいなあと思います。その門があっても無くとも東高校の校舎というのは抜け出ようと思えば、どっからでも抜け出れますよね。 私なんかしゅちょう抜けだしていったもんです。けれども、そうであってもあの門というのは東高のシンボルであろうと、そんなふうに思ったわけであります。 1990年10月26日50周年記念講演「史眼の必要な時代」より 北海道新聞社編集局長 作田 和幸氏 (東高1回生) |
||||||
| 注: この門(=右上写真2007.10.8撮影)は、2度位置を変え、真新しい「市立函館高等学校」という校名を掲げて現存する.。門の扉を閉めない伝統は今も生きている。今日でも何人でも出入り入ることが可能だ。体育の日、この校門を通って中に入ると、「おはようございます」と後輩女子達が声をかけてくれた。「おはよう」(尚、防犯上、監視カメラが各所に設置されている) | ||||||
| ☆私の中の東高(抜粋)☆ | ||||||
........... 私の高校時代――得たことはたくさんあったはずなのに強烈にうかんで来るシーンが、たった二つしかありません。 私の高校時代――得たことはたくさんあったはずなのに強烈にうかんで来るシーンが、たった二つしかありません。それは、無残にパワーシャベルで打ちこわされていく旧校舎の姿です。シャベルが一振りする毎に、木造校舎はあっけないほどあっさりと崩れていきました。私たちは、あったかな明るい新校舎の大きな窓から、それをただ見ていました。それは、非情な文明の力でした。 ただ黒い木片となった思い出の校舎は、数日のうちに片付けられ、私の心にただ、何かを残しました。今思い出す。高校3年間の思い出が、たったその3分の1を過ごした寒い校舎の出来事であるのは、なぜでしょうか。あの多感な時期、誰へともなく味わった怒りと寂寥感は、今も私の中に生きつづけているように思えるのです。 ふとこんな事を思い出しました。それは、確か私が1年生の秋、まだ旧校舎もあった頃です。白いモクレンの花がハラハラ落ちて、少し寒くなりかかるような季節だったと思います。私は友人たちと玄関のそばで話をしてました。夕方でした。 そこに、一組のカップル(今思えばご夫婦なのです)が、ゆっくり歩いて来、私たちはハッとしました。女の人のおなかが、大きかったのです。そのお二人は、なつかし気に古びた校舎を見上げながら、何も言わず、またゆっくりと校舎づたいに歩いていきました。お二人は多分卒業生、なつかしい学舎に会いに来たのでしょう。 私たちは、毎日で精一杯、卒業後の事など全く見えない若さでした。しかし、そこにいた者皆が、その時、なにやら言葉にできないこれまでつづいていた遠い遠い時の流れと静かな「伝統」を感じ、東高への愛着のような安らぎを覚えたのです。  7月2日、この原稿依頼が届いた日、私は函館におりました。昭和59年7月2日、当時の校長、及川哲哉先生が亡くなった日です。 7月2日、この原稿依頼が届いた日、私は函館におりました。昭和59年7月2日、当時の校長、及川哲哉先生が亡くなった日です。私は今、田舎で小学校の教師をしています。進路が定まらずにいた高三の初夏、及川先生との出会いが、そして先生の日の死が、私の進む道を決意させたということができるかもしれません。無論、今まで出合った人や出来事すべてが、今の私を支えていることには違いありませんが、うまくいかず苦悩することの多い日々、及川先生の深い情や、奥行きを感じさせた心と何よりも東高への情念を思い、又時折、先生によって命名された「青雲の樹」の前に立ち、自分を見つめなおしてみたりすることもあります。 ....... どんな形であれ、そこに生きる学生はいるけれど、言葉ではなく深く静かな思い「伝統」を色濃く残していた時代に、又それが新しいものへ変わっていく過度期に東高校で様々なことを学ばせてもらったことを、深く感謝しています。 35回生 滝本美佳子さん |
||||||
| ☆旧校舎のことども☆ | ||||||
 「十年一昔」という言葉があるが、私が卒業してからはや十年の月日が経とうとしている。私たちのあの懐かしい「オンボロ校舎」は、今ではその跡形もない。私たちの学生は3年間ずっと旧校舎で学んだ最後の生徒であった。それだけに、私の同期生やそれ以前に卒業した諸先輩たちにとって、それぞれに旧校舎での思い出は数多くあると思う。 「十年一昔」という言葉があるが、私が卒業してからはや十年の月日が経とうとしている。私たちのあの懐かしい「オンボロ校舎」は、今ではその跡形もない。私たちの学生は3年間ずっと旧校舎で学んだ最後の生徒であった。それだけに、私の同期生やそれ以前に卒業した諸先輩たちにとって、それぞれに旧校舎での思い出は数多くあると思う。旧校舎についての思い出をいくつか上げて見ると、まず、夏は非常に暑く、冬は非常に寒いという正に「冷暖房完備」の校舎であったということである。特に、夏や秋の雨の降る時期には、教室や廊下の所々で雨漏りしバケツが置かれていたり、冬は窓のすき間から冷たい風とともに、雪が入り込んでくることもあった。そのため、窓のすき間にガムテープを貼ってしのいだのである。 また、冬になると、日直が朝早く来て石炭を取りに行き、石炭ストープに火をつけなければならなかったが、そうして焚いたストーブの上に、4時間目にやかんをかけてお湯を沸かし、カップラーメンを食べたりするなどといった楽しみもあった。 .......... 今、私の勤務している学校に何と、東高の卒業クラスの同級生が3人席を並べて仕事をしている。この他に、同期生が一人、大先輩が二人あり、毎日が同窓会(?)の気分である。「今蘇る曙の 希望の調べ丘に満ち、....」を時々口ずさんでいる事がある。このことからも「青雲の志」で結ばれた強い絆を感じている今日このごろである。 校舎はすっかり変わったが、東高は私たちの永遠の母校である。 32回生 堂前 義則さん |
||||||
| ☆旧校舎では石炭当番があった☆ | ||||||
|
||||||
| ☆私の思い出☆ | ||||||
 旧校舎は、トイレが特にひどかった。職員便所は、男女約80人に大が2つのみ。この便所にまつわる珍談奇話は多いが、ここでは遠慮することにしよう。そこで。生徒のトイレの話を書こう。 旧校舎は、トイレが特にひどかった。職員便所は、男女約80人に大が2つのみ。この便所にまつわる珍談奇話は多いが、ここでは遠慮することにしよう。そこで。生徒のトイレの話を書こう。冬のある日、真っ青な顔をして女性徒がやって来て、便所の下の方(便槽)で何かが確かに動いていたと言う。指導部の私に見てほしいというわけだ。その時は結局なにも探せず、その生徒の錯覚ということに落着いた。ところがそれから数日して、再び別の女性徒が二人便槽に誰かがいると駆けこんだ。この時も体育館入り口のトイレ。早速、2.、3人で走った。よくよく調べてると、グランド側に入口のある外の便所の中からもぐりこんだ形跡が発見された。もう少し早ければ、このクサい者を逮捕できたと思われる。その後すぐ外側便所は厳封されたが、それにしてもあの汚い、狭い入口から忍びこむとは御苦労なことひとしきり。現校舎の、清潔で明るいトイレに入ると、この事件を妙に懐かしさで思い出す。 以上らちもない思い出ばかりで恐縮する。私の記憶違いがあって、あるいは独断に陥ったところもあるかも知れない。しかし、私にとってのかけがえのない30代の懐かしい1ページとして許していただきたい。 伊藤 義造先生 (注:函館東高の閉校式にこの男子便所の写真が紹介された時、若い女性から驚きの声が上がった。) |
||||||
| 伊藤先生は元気でご活躍されている。メールにて引用のお知らせをした。 「わざわざの挨拶恐れ入ります。
大変素晴らしいホームページですね。これからも折に触れてゆっくり読ませていただきます。
ますますお元気でご活躍ください。
伊 藤 」 2007.10/15 15:17
|
||||||
| 番外 ☆質問コーナー トイレに明かりを☆ | ||||||
| 問 クラブで遅くなってからトイレに行くと暗くて危険ですから、照明をつけて欲しいと思います。 <1年女子> 答え 考えていましたが、予算の関係で今年つけることがことができませんでした。新年度にはつけることができるように努力したいと思ってます。 <太平先生> 昭和42年8月11日「青雲時報」第74号 |
||||||
| ☆東高校50年☆ | ||||||
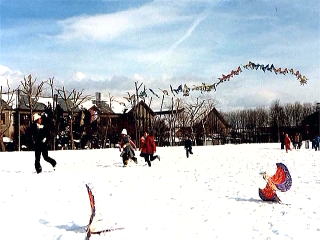 〔幸せな奴だナ〕と呟いている。 〔幸せな奴だナ〕と呟いている。昭和16年、市中2回生として入学、平成元年母校である東高の教師を退職した。 船見町の坂上の仮校舎から柳町の木造2階建の新校舎で学び、その後教師として平成元年に至るまで、一度の転勤もなく、しかも素晴らしい環境の中、で感動をつたえる美術を担当できたことを思うと、その僥倖に胸が熱くなる。 ........(割愛)........ 『東高の卒業生だということは、すぐに判りますね』市や企業に勤めている先輩の卒業生が云う『どこか抜けているんです』 しかしその口調は明るく、なにか誇らしげである。抜け目なく立ちまわり、競争相手を蹴散らしていくよりも、熱心に努力しながらもドジった所のある性格、そんな愛すべき連中が多いと云うのだろう。そして、なによりもそれを笑って理解しあえる気風があると思うのだ。 でも誤解されては困る。努力もしないで失敗ばかりしている者を庇うというのではない。懸命に励んで全力をだしつくした選手が敗れた時、彼等に送る拍手の中心に東高の卒業生が多いということなんだ。 ........ 60年間の間に東高で培われた苗木は各地で立派な大樹に成長した。函館市だけでも、木戸浦隆一市長を始め、同窓会の発展に尽力された沼崎弥太郎氏、田中仁氏、柳沢勝氏は函館経済会のリータ゜である。もちろん、その他にも多数の卒業生諸氏が活躍されているのだが、なにか彼等の中に共通しているものがあるような気がしてならない。 〔青雲の志〕それは生涯を賭けても悔いのない希望の星を求めることだろう。その星が何であるのかを考えられる豊かな土壌が、幸いなことに東高校にはまだ残っていると思うのだが―― ........そして私を駆り立てるエネルギーは愛する東高で養われたものであることに間違いない。 ........ もうすぐ前夜祭の若々しい歓声が夜空に響きわたるだろう。胸を張って叫んでほしい。『函館東高・万歳!』 梅谷 利治先生 (梅谷先生については「凧士梅谷利治先生の世界」を参照ください1 |
||||||
|
||||||
 当時の校舎の写真が嬉しいです。窓は二重の木枠で、廊下にすきまから吹き込んだ雪がうっすらありましたね。石炭当番というのがあって、油につけたオガタンに新聞紙から火をつけて石炭を燃やしてた、なんて事、思い出しました。上京して30年になりますが、こちらで公立だけど私服だったとか、学園祭は行灯で市内を練り歩くとか、合唱祭では当時映画で流行ったサタデーナイトフィーバーを皆で踊ったとか言うと、皆おどろきましたね。
当時の校舎の写真が嬉しいです。窓は二重の木枠で、廊下にすきまから吹き込んだ雪がうっすらありましたね。石炭当番というのがあって、油につけたオガタンに新聞紙から火をつけて石炭を燃やしてた、なんて事、思い出しました。上京して30年になりますが、こちらで公立だけど私服だったとか、学園祭は行灯で市内を練り歩くとか、合唱祭では当時映画で流行ったサタデーナイトフィーバーを皆で踊ったとか言うと、皆おどろきましたね。