|
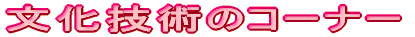
�͂��߂�
�@�u�Q�P���I�̓��{�͕����Z�p�̌��オ���W�̊�b�v�Ƃ̔F���ɗ����A�킪���̕����Z�p�𑽖ʓI�Ȏ��_���猟�����A�����Z�p�U���̉ۑ�ƕ����T��B�Ȃ��A�����̐��ʂ́A�u�����Z�p�̔�r���x���́v�Ɏ��Z�߁A�{�R�[�i�[�Ɍf�ڂ���B
��1���D�����Z�p�̔�r���x����
�@��1�́D�����Z�p�Ƃ� about liberal arts (14.09.11�X�V)
�@�@�@��2�́D�����Z�p�̕��@ theory (10.03.31�X�V)
�@�@��3�́D�O�ؐ��ƕ����Z�p�@K. Miki & liberal arts (14.11.25�X�V)
�@ ��4�́D�����Z�p�̎j�I�W�J history�@�i�ȉ��E�\��j
�@�@�@��5�́D�����Z�p�̌��� current situation
�@�@�@��6�́D�����Z�p�U���̐���ۑ� political issue
�@�@�@��7�́D���ʊe�_ selected countries
��2���D����ɐ�������{�̔��ƕ����Z�p�i�����N�j
Japanese sense of beauty &
liberal arts (link)
�@ ���{�̌����i�@ http://sugikei55.exblog.jp/ �@
�����̍��|cherry flowers in
Tokyo
��b�R����E��{�E���g����|
Enryakuji
Temple�ESakamoto�EHiyosi Taisya Shrine
�@�@
���s�E�c���̍��|cherry
flowers in Kyoto & the Imperial Palace ��
�A �u���{��S�҂̌J�茾�v
http://www13.plala.or.jp/nihongomoja/
�|���Ђ�����{��ɂ��Ă̌��|
���͓ǖ{�����{�ꋳ���{�ɂ��čl�B�����āA�u�����V���v����肰��B
�����V��
�J�菁��Y �w���͓ǖ{�x
�g�s�~�V��E�I�@���{�y���N���u�E�� �w���͓ǖ{�x
��[�N��
�w�V���͓ǖ{�x �����ȏo��
�O���R�I�v �w���͓ǖ{�x ��������
�����^��Y �w���͓ǖ{�x �V������
�ےJ�ˈ� �w���͓ǖ{�x �������� 2006�N
��
�B ���ʋ��t�Ƃ��ēǂu���͓ǖ{�v�@���s��v���@���e�Ё@2019�N3��28�����s�@ 
���N�������Đςݏグ�����͘_�𐢂ɖ₤���߁A�X�̕��͂̓Y��������A�˂�̂łȂ��A�������畂����ł���^�ɋK�͂ƂȂ镶�͂̎p�����Ԃ�o���A�u��ʑ��v���܂Ƃ߂��Ȃ����A�Ɖ��߂Ďv�����B�ȉ��͂��̓w�͂̐Ղł���B�i�͂��������甲���j
��3���D�G�L
���z �u�P�Y�Ȃ��҂͔@���ɂ��čP�S���������邩�v�i15.01.30 �L�j
��N�A���N�Ƒ������œ�����ɏo�Ȃ����B��́A���z���w�Z6�N2�g�̃N���X��ł���A������́A����o�ϊw�� ����̓[�~42�N���̃[�~��ł���B���ɏo�ȗ��͗ǍD�ł������B��70���A�Ê�Ƃ��Ȃ�ƒN�����Ⴂ���낪���������v����̂ł��낤�B�v���Ԃ�ɍĉ��ƍ����̂����ɐ̂Ƀ^�C���g���b�v���A�v���Řb��ߋ��ɉԂ��炩���āA�y�������Ԃ��߂������B
���ɏ��w�Z�̃N���X��́A�o�Ȏ҂��j�������ł���A�܂��A���ƌ�̌o�����l�X�ł��邱�Ƃ���A�F�X�Ɩʔ����b�������Ă����ւ��[�����̂��������B
���Ԉ�ʂł͘V��̒j���͏����ɔ�ׂČ��C���Ȃ��ƌ����邪�A���̃N���X��͒j���w�����c�ƂȂǂŎd���𑱂��Ă���l�������������A�����w�ɕ�������炸�ӋC���V�ł���A���C�̂��������ɗa���邱�Ƃ��ł����B
���͂܂������̂��납�烊�^�C�A��̐�����S�҂��ɂ��Ă���Ƃ��낪�������B��ɂ́A���Ǐ��ł������Ėڟ��́u�����v��u���ꂩ��v�Ȃǂɓo�ꂵ�Ă���A�����뉽�����Ă��镗�ɂ������Ȃ��̂ɗD��ɕ�炵�Ă���u�����V���v�̐��E�Ɉ�퓲�������Ă�������ł���B�܂��A�h�C�c�ł͎Љ�ۏႪ�s���͂��Ă��邱�Ƃ���60�Ń��^�C�A���邱�Ƃ�҂��]�ސl�������Ɖ����œǂ��Ƃ��e�����Ă���B
����A�d������������S�����R�ɂȂ邱�Ƃɉ��������̕s���������Ă����B���C�Ƃ��������悤�̂Ȃ��q�b�g���[�̃i�`�Y���ɓ����̃h�C�c���������Ă̐��������Č}�����ꂽ�̂́A���R�ł����Ă����_�I�ɕs����ȏ��瓦��đ�����]���炾�ƁA�G�[���b�q�E�t�����́u���R����̓����v�ŋL�q���Ă���B���R�ł��邱�Ƃ͕s���̂��Ƃł�����B
�����āA�V��ɂ͌o�ϓI�ȕs��������B�Ⴂ�Ƃ��̕n�R�͉��Ƃł��Ȃ邪�A�N�Ƃ��Ă���̂���͎S�߂ł���B���鎞�̃[�~�ő���搶���u�P�Y�Ȃ��҂͍P�S�Ȃ��v�ƌ���ꂽ�B�}���N�X�o�ϊw�҂炵����ʌ��t�Ƒ�����a���������ĕ��������A���̌��t�������痣�ꂸ�A���ł͍��E�̖��̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B
����ł́A�u�P�Y�Ȃ��҂͔@���ɂ��čP�S���������邩�v�B���̑喽��Ƀ��^�C�A����10�N�߂��o�߂������݁A�����ǂ̂悤�ɑΉ����Ă������A�܂����̈����ė���R���͉��ł����������A�v���o���܂܂ɏ����A�˂邱�Ƃɂ���B
�@�ŋ߂̂͂�茾�t�ɁA�u�V��̓L���E�C�N�ƃL���E���E���K�v�ł���v�Ƃ����̂�����B���߂Ă��̌��t�ɐڂ������A�܂����ɕ����̂́u����v�Ɓu���{�v�ł���B���ꂪ���́A�u�V��́A�����E�s���i���j�ƍ����E�p���K�v�v�̊|�����t�ƒm���āA���܂����Ƃ��������̂��Ɗ��S�����B
�@�×��A���l�Ջ����ĕs�P���Ȃ��ƌ�����B�܂��A�߂�����͋y���邪���Ƃ��Ƃ������B�d�������������̂͂��肪�������A�Ƃɂ����ɂ����肷���Ă͍���B�����Ŋe���A�Ȃ̍ˊo�ŁA�u�����s���v�Ƃ����T���A�u�����p�v����邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�́A�u���e����w�K�v�A�u�͌�v�A�u�z�[���y�[�W�쐬�v�̎O��C�x���g�����������ɂȂ��Ă��ꂽ�B
�@���h���́u�Ԏq�ƃA���v�őS���I�Ɉ���L���ɂȂ������m�p�a���w�@�̐��U�w�K�Z���^�[���e����R�[�X�ɒʂ��n�߂�3�N�o�B�u���e���������Ă��܂��v�Ƙb���ƁA�u���Ń��e����Ȃ̂ł����H�v�Ƃ������₪�A���Ă���B���̐S�́A�u���܂��玀��ɂȂ������e����������Ȃ�ĉ��ƕ��D���Ȑl�v�Ƃ����Ƃ���ł��낤���B
�Ƃ��낪���e���ꈤ�D�҂͌����ă}�C�i�[�ȑ��݂ł͂Ȃ��B���ɁA���n���搶�i���ێЉ�w�������j�̂��w���ōw�ǂ��Ă���J�G�T���u�K���A��L�v�̃N���X��20�����A�����͖��ȏ�Ԃɂ���B���k�͂قڒj�������ŏ�����50�`60�Α�A�j����60�`70�Α�Ƃ����Ƃ���ł��낤���B���̔N�オ�����ɕ����I�����ɊS���[�������킩��B
�@���e����Ɠ��m�p�a���w�@�͒��w���i���z�w���j������̍���̉Ԃł������B���e����̓w���}���E�w�b�Z�́u�ԗւ̉��v�Œm��A�����Ƀ��[���b�p�̃��}�����������B�܂��A���m�p�a���w�@�͎o���Z�ƕ�������A���̕��̋L�͂��b���F�̃X�J�[�t�͓���̑Ώۂł������B���z�w���͍]���f�Z���P�W�X�T�N�ɓ��m�p�a���w�Z�i���m�p�a���w�@�̑O�g�j�̗אڒn�ɂ������������\�W�X�g�n�̓��m�p�a�w�Z�i�j�q�Z�E��ɔp�Z�j���ɓ��m�p�a�w�Z�q�풆�w���Ƃ��đn�������̂��O�g�ł���B
���܂��܁A�V�O���z�������̔N���}���āA���̓�̍���̉Ԃɂ��߂Â���������A���ԁE��Ԃ��щz���A���[���b�p�n�}��Ў�ɉ͂���ɑ�������A�X�ɍs������Ղ��A��ǂɓ�V���Ȃ�����J�G�T���̐��E�ɐg��u���̂͏��Ɏ����̎��ł���B����ɂ́A�w�K���Ԃƈꏏ�Ɂu�K���A��L�c�A�[�v��g�����Ƃ��A���e������x�[�X�ɓ������}���X��n�̃t�����X��E�C�^���A��E�X�y�C����֒��킵�悤�Ƃ����͖����ɍL����B
�@�͌�͓����ꎞ��Ɋo�����B�ꎞ�͈͌镔�ɏ������A�V�����ՂɌ�����قǁA�̂߂荞���Ƃ�����B�Љ�l�ɂȂ��Ă���͂��܂ɓ��D��őł��x�ł��������A���^�C�A������A�w�m��̈͌镔�ɏ������Z�i�őǂ��Ă���B�����R�N�]��͐_�J���߂��̃z�e���R�V�K�ɂ���u��i���V���H�j�Ɉ�ԋ߂��v��ɂ��Ă���͌�T�����ɒʂ��Ă���B
�@����̑����͔N�z�҂ł��邪�A�Ď����z����������̕��������̑\���ɂ���������悤�ȎႢ�C���X�g���N�^�[����Ɉ͌�ɔM�����A���̊Ԃ͓�����Ɏ�Ԃ����悤�Ɍ�����B����͊w�m��̈͌镔�ɂ����ʂ���̂����A���ۂ̂悤�ɒʂ��Ă���l������B�͌�T���������h�ɋ��ꏊ�i�u�����E�s���v�j�̖������ʂ����Ă���A�͌�قǍ���Љ�ɓK�����Q�[���͂Ȃ��Ǝv���Ă���B
�@�͌�͊����E���o���i��E�]���h�����邱�Ƃ��炻�̋�����ʂ�F�m�ǂ̗\�h���ʂ����ڂ���Ă���B���勳�{�w���ł��P�ʎ擾�\�ȍu���Ƃ��đg�ݍ��܂�Ă���A�Αq9�i�i���z���Z�E����@�w���E����o�R�Ńv�����m�ɓ]���j���A�v�����m���w���ɓ������Ă���ƕ����B
�@�͌�T�����ł́A�@���i���{���@�̃v���{�������j�o�g�ŏ����A�}�I�茠�ɗD���o���̂��邨��l�ɂ��w�������Ă���B���܂��ܑ����Ē����x�ɂɓ����邽�ߓ����̓p�\�R���͌�\�t�g�Ŋ��͌����}��A����l�̕��A��҂Ƃ��Ǝv���Ă���B�ŋ߂̈͌�\�t�g�̓����e�J�����@�����Ĉȗ���̑O�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǐi�������B�����g�p���Ă���\�t�g�͕��{9�i�ɂS�q�Ŕ������������ƌ�����B�ŋ������N�̂S�i�ɂ͖ő��ɂ����肵�Ē��������������i�̂R�i�~�܂�ʼn������v�������Ă���B�͌�\�t�g�̗ǂ��Ƃ���́A�����̍D���Ȏ��ɍD���Ȃ����ǂł��邱�Ƃł���B���Ƃ��đł����ɕ�̂���̂�����A�Ƃɂ������ł��ōU�߁E�����̋����͖��ނł���B
�@�z�[���y�[�W�̍쐬�̓��^�C�A��Ɋ�����Е����Z�p��ݗ��������ƂŃX�^�[�g�����B������ЂƂ͖�����ŁA�͂��ȕs���Y�����Řd���A����@�g���u���m����v�̒��Ō��y������c���^������Ђł���B�i�n�Ӑ��u��c���^������Ђ̎��{�s��\�z�v�o�σZ�~�i�[2007.1�j
�@�����Z�p�̌����Ɠ��O�o�ρE�S�|�f�[�^�[���C���^�[�l�b�g�Œ��邱�Ƃ��ړI�ŁA���X���郊�s�[�^�[�̑��݂��z�[���y�[�W�^�c�̃C���Z���e�B�u�ɂȂ��Ă���B���v�f�[�^�[�͖����̂悤�ɔ��\�����̂ŁA�K�R�z�[���y�[�W���قږ����X�V����B������n�߂����A�ł��̓��ɂ��ׂ����Ɓi�u�����E�p�v�j����������Ă���̂�������B���T���j���Ɍf�ڂ������o�V���̓��v�����f�[�^�[�x�[�X�ɃO���t���������̂���{�ł���B�ŋ߂͓��Ă̊����E�בցE���������̓����ɒ��ڂ��I���W�i���f�[�^�[����쐬�����O���t�����M���Ă���B
�@���̃O���t�D���͌���H��Ƒ���搶�ɍs�������B�搶�͓������͓I�ɓ��{�o�ς͂��������������Ă����B���鎞�̃[�~�Łu�o�ϕ��͕͂����������܂�A��͒P����Ƃʼnc�X�ƃf�[�^�[���v�Z���ăO���t�����邾���ł��B�v�ƌ���ꂽ���Ƃ�����B�ȗ����̂��Ƃ����H�����݂Ɏ����Ă���B
�o�σf�[�^�[����X�ǂ����Ƃ́A���O���킸�Љ�̓����ɐړ_�����������邱�Ƃɒʂ��A�傫�Ȍ��p�̈�ƍl����B�ߔN�́u�����v�Ə̂��ēy�������������A���o�V���ƃ��e����̃e�L�X�g�������ċ߂��̃R�[�q�[�V���b�v�ɒʂ��̂����ۂł���B�o�ϖʂ𒆐S�ɂR�O���قǐV���ɖڂ�ʂ��ƁA��͂P���Ԃقǃ��e����̗\�K������B�P���̎n�܂�ɐg�̂Ɠ��]�������Ƃł��̓����X���[�Y�ɉ߂�����B
�����ŁA���^�C�A��̃��C�t�X�^�C�����l����ɓ������Ď����傫�ȉe����������l�A�̒O��ꉄ���ƍ��X�؊�N���ɂ��Ă��Љ���Ē��������B
�܂��A�O�͋����l�Z�E����o�ϊw���E����w�@�𑲋Ƃ���A���H�g���������ɂɓ��Ђ��ꂽ�B�����������������Ɏd�������ꏏ�����Ē������̂ł��邪�A�A�C�f�A�L���ȈِF�̋��Z�}���ŁA�G�R�m�~�X�g�Ƃ��ėD��Ă�������łȂ������ɂ������A�����E�W��ЎВ����C���ꂽ�B
�ޔC��̓r���̂P���ɏ����Ȋw�[���\���Ď��M�����ɐ�O����A���ɂ͏��K�͂ȕ�����Â��ꂽ�B�����^�C�H�ƏȂɂQ�N�o�����Ė߂��Ă�������A�u�t�Ƃ��ČĂ�Œ��������Ƃ�����B�N���b�V�N���y�ƈ͌�E�S���t������Ȃ������A�������v�ȓ����ŃT���g���[�z�[���ɃR���T�[�g���ɍs�����B����Ȃ���䂪����́u�����V���v��n�ōs�����C�t�X�^�C���ɂ͌h�������A�܂��A�܂��������������̂ł���B
����������̍��X�؎��͋�����Z�E����@�w���𑲋Ƃ���A�x�m���S�ɓ��Ђ��ꂽ�B�V���S�ł͕��В����߂�ꂽ��A�n��d�FҰ����ɏA�C����A�d�F�c�̉�Ƃ��ċƊE�ĕ҂Ɏw���I�������ʂ����ꂽ�B���͋�����ǂ̗���ł��ꏏ�����Ē��������A��a�������ꂽ����Œ��g����̉p���a�m�ł������B
���͕��В������A��Ɍo�c�A��ɏA�C���ꂽ����h���ƍŌ�܂ŎВ��|�X�g���������ƌ����钴�啨�ł��������A�u���R�́v�Ɓu�����ł��邱�Ɓv�����b�g�[�ɂ���A�S���̂Ԃ�Ƃ��낪�Ȃ��B�N���x������◝����̑O�Ɏf���āA���ɂ̓n�C�G�N��P�C���Y�����p�����b������������̂��y���݂ł������B���i�͏t���l���Ƃ��Ă���ꂽ����U�A����ۏ؍��̕ۑS�������Ă���s��ƒՔ��荇���̌��ɂȂ�ƁA�ؔ��������ɂ��ւ�炸����̗���d���A������ɗL���ȉ�����ɓ����Ă�����r�͗��Ǝv�킹����̂��������B
�܂��A�V���S�ł͘J���E�l�������������Ƃ������āA�Ǝ��̘J�g�ςƎ��{��`�ς��������ŁA���i���h�E�h�[�A�̒����Ɏ����̌������Љ��Ă����Ɗy�����ɘb������Ă����̂���ۓI�ł������B�C�O�W���[�i���X�g�̃C���^�r���[�����邱�Ƃ�����A������ɂ��ւ�炸����I�ɉp��b���b�X��������ȂǁA���̒m�I�D��S�������������鐶�����ɂ͋������������B
���낻�떇�������A�u�P�Y�Ȃ����͔̂@���ɂ��čP�S���������邩�v�̑喽��ɉ��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����t��ɉ߂��邪�A��͂�u�V��͋���Ƌ��{���K�v�v�Ƃ������Ƃɗ����Ԃ�̂ł͂Ȃ����B����搶�̌���ꂽ�u�P�Y�v�Ƃ́A�s�т̒�q���鎄��������������I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���_�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�������ĉ��ƂȂ����S�����B
�����ݐЂ������̌o�ϊw���́A���ȂQ�ނ���قڎ����I�Ɍo�ϊw���ɐi�����Ă����B���݂͑������ꂽ���A�i��������Ȃ�A���Ȃ̌o�ϊw���i�w��]�҂Ƙg���������Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƕ����Ă���B���̂��Ǝ��̂͐��k�ْ̋��������߁A���x������Ɏ����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����A�o�ρu�w�v�ɂ͌o�ρu�y�v�i�o�ς��y���ވӁj�̑��ʂ����邱�Ƃ�搶���̓��̕Ћ��ɒu���Ē�����ƍK���ł���B
�Ō�ɒ��܂�Ȃ����͂���߂�퓅��i��p���A���яG�Y�̃G�b�Z�C�u�K���A��L�v�i�����j�Œ��߂����Ē����B
�u���������������ˌ�����ꕺ���̖��܂ł�������̐푈�̒B�l�ɂƂ��āA�푈�Ƃ������̂͂��鋐��ȑn��ł������B�m��s�������ޗ��������Ă��銴���Ƌ�z�������ʉc�X����J���A����͖��厍�l�̎d���̌����ł���B�K���A��L�Ƃ����n��]�k���A���̂悤�ɖl�����̂ɕs�v�c�͂Ȃ��B�T���_���̉�����������A���Ԃ���ы���B�v
�i�{���͓�����w�o�F��u�o�F190���v<2014.10���s>�Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ł��B�j
���яG�Y�����I�@��
�u�K���A��L�v �i14.11.18 �L�j�@
�@
�V�B�U�A�̋L�q�̐��m���́A�w�ғ��̓����ɂ���ďؖ��ς݂����������A�ޓ��������ɍۂ��A�n������@��N���Ċ��Q���������m��ʃ��I�}�̐폟�L�O��̔j�Ђ̗l�ɁA��L�͖l�̑O�ɂ����ꂽ�B�̃U���U�������ʁA�������̐��A�m���ɂ���ȕ��Ɋ�������B�́A���t���A�ɍ��܂ꂽ��A�����ɏĂ�����ꂽ��A�M�Ŏʂ��ꂽ�肵�āA���̊함�̗l�ɁA���J�Ȉ������Ă��������A�����Ƃ������͉̂���ƌ������]���ڕ��̂������������̂��̂������ɑ���Ȃ��B
�u�K���A��L�v�́A���n����̊ԂɁA�����ׂ������ŏ����ꂽ���V�@�ւ̕��ɉ߂��Ȃ������ł���B�����A���́A�l�́A�������̂Ȃ��������̌����ǂނ̂��낤���B���������������ˌ�����ꕺ���̖��܂ł�������̐푈�̒B�l�ɂƂ��Đ푈�Ƃ������̂͂��鋐��ȑn��ł������B�K���A����Ƃ����n��ŁA�ނ͒ʋł��Ȃ�������Ђ̍ޗ����Ȃ������ł��낤�B�m��s�������ޗ��������Ă��銴���Ƌ�z�������ʉc�X����J���A����͖��厍�l�̎d���̌����ł���B�K���A��L�Ƃ����n��]�k�����̂悤�ɖl�����̂ɕs�v�c�͂Ȃ��B�T���_���̉�����������A���Ԃ���ы���B
�u����Ƃ������v �i09.11.22 �L�j�@
�u���]�A��ЂɁA���͂�Ă���Ȃ��̂܂˂�����Ȃ��[�́A�\�T�t�̌�O�ɂāA�邤���[���A�l���Â܂�Č�A�Ă��Ƃ��Ă��Ƃ��ƁA�Â݂����āA�S���܂����鐺�ɂāA�ƂĂ������Ă���A�Ȃ��Ȃ��Ƃ����Ђ���B���S��l�ɂ�����ĉ]�A��������̗L�l���v�ӂɁA���̐��̂��Ƃ͂ƂĂ������Ă���B�Ȃ��㐢�����������ւƐ\���Ȃ�B�]�X�v�i���j
����́A�ꌾ�F�k���̂Ȃ��ɂ��镶�ŁA�ǂ��A�������͂��ƐS�Ɏc�����̂ł��邪�A����A��b�R�ɍs���A�R�������̕ӂ�̐t���Ί_���߂āA�ڂ���Ƃ�����Ă���ƁA�ˑR�A���̒Z�����A�����̊G�����̎c���ł�����l�ȕ��ɐS�ɕ��сA���̐߁X���A�܂�ŌÂт��G�ׂ̍����ȕ`����H��l�ɐS�ɐ��݂킽�����B����Ȍo���́A�͂��߂ĂȂ̂ŁA�Ђǂ��S�������A��{�ŋ���������Ă���Ԃ��A���₵���v�������Â����B�i�ȉ����j
�m���ɋ�z�Ȃ����Ă͂��Ȃ������B�t�����z�Ɍ���̂��A�Ί_�̑ۂ̂�����A��S�Ɍ��Ă����̂����A�N�₩�ɕ����яオ�������͂��͂�����H�����B�]�v�Ȏ��͉���l���Ȃ������̂ł���B�ǂ̗l�Ȏ��R�̏������ɁA�l�̐��_�̂ǂ̗l�Ȑ��������������̂��낤���B����Ȏ��͂킩��Ȃ��B�킩��ʋ���ł͂Ȃ��A����������̍l���������Ɉ�Ђ̟����ɉ߂��Ȃ������m��Ȃ��B�l�́A��������[�����肽���Ԃ������������v���o���Ă��邾�����B�����������Ă���؋��������[�����A���̈����͂�����Ƃ킩���Ă���l�Ȏ��Ԃ��B���_�A���͂��܂��v���o���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂����A���̎��́A���ɍI�݂Ɏv���o���Ă��̂ł͂Ȃ��������B�����B���q��������B���������m��ʁB����ȋC������B�i�ȉ����j
���Ɏv���o�����͔��ɓ���B�����A���ꂪ�A�ߋ����疢���Ɍ����Ĉ��̗l�ɉ��т����ԂƂ��������߂��v�z���瓦���B��̖{���ɗL���Ȃ����̗l�Ɏv����B�����̊��͂���̂��B���̐��͖���Ƃ͌����ĕ����Ƃ����l�Ȃ��̂ł͂���܂��B����͊@���Ȃ鎞��ł��A�l�Ԃ̒u�������̓����I��Ԃł���B����l�ɂ́A���q����̉������̂Ȃ��[�قǂɂ��A����Ƃ��������킩���Ă��Ȃ��B��Ȃ���̂�������������ł���B
�i���j�u�ꌾ�F�k�v�����r��Z���@�����܊w�|���Ɂ@������p
����l�̂͂Ȃ��B��b�̎R�������ŁA�킴�ƛޏ��̎p�������Ⴂ�������A�\�T�t�̑O�ŁA�邪�ӂ��A�l�������Ȃ��Ȃ�������A�e���g���g���ƌۂ�ł��A�S�̐��݂��������ŁA�u�ǂ��ł����\�ł������܂��B�ǂ����ǂ����v�Ƃ��������B���̈Ӗ�������l���疳���ɂ����˂��āA�u������܂�Ȃ����肳�܂��v���܂��ƁA���̐��͂ǂ��ł��\���܂���A�ǂ����㐢���������������܂��Ɛ\���������̂ł��v�Ɠ������悵�B
�u��� �� �搶�@���ʂ�̉�E�Âԉ� �v�ɏo�Ȃ��ā@�i09.07.24 �L�j
�@7��23���A�搶�̂��ʂ�̉��200���̗�Ȃ̂��Ɗw�m��قōÂ���܂����B
�@�����̕��X���S�̂����������ʂ�̌��t���q�ׂ�ꂽ��A�ߎq�v�l���炲���A���������܂����B�搶���a���ł̂��l�q���ƒ�l�Ƃ��Ă̓��퐶�������b�́A���ɂ̓��[���A�������Ȃ�����搶�ւ̐s�����ʈ��ɂ̎v�����������܂����B
�@���i���h�E�h�[�A�����́A���Ă������̒��ŁA�搶���u�������肵���l�v�A���Ȃ̎v�z���m�������l�̈ӌ��ɘf�킳��Ȃ��l�ƕ]���A�o�ϊw�݂̂Ȃ炸�v�z�j�ɂ����Ă��傫�ȑ��Ղ��c���ꂽ�Ə̂��Ă����܂����B
�܂��A���t�̘J���Ƃ�ꂽ���P�Y���i�ꍂ������j�́A���x�����A�[�c�ƌ�i�琬�ɂ�����搶�̔M���v��������I����܂����B
�@�搶�͗90���߂��ď����낵�́u����͌o�ϊw��n�S8���v����������܂����B�ŏI���u���{�o�Ϙ_���v�̒��œƎ��̌�����W�J���ꂽ���L��u�_�ѐ��Y�Ƃ̏��Łv�Ȃǖ����̏͂́A�搶���������ׂ��ۑ�Ƃ��Č㐢�̎��������ɓ���������ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƁA�Z�����Ϗ����ꂽ�Ċ_�a�v���i���喼�_�����j���q������Ă��܂����B
���̐搶�̎u��[���~�ߎ����Ȃ�ɐ��i���čs�����Ƃ��A��Ɏc���ꂽ��X�̍Œ���̓w�߂ƁA�z����V���ɂ��܂����B
���O���͖k�i�� �i09.05.07 �L�j
�@��������ȍ~�A�ԂƂ��������Ӗ�����قǁA���͂킪�����\����ԂƂ��Đe���܂�Ă��܂����B�܂��U��ۂ̂悳���畐�m���̏ے��Ƃ������ȂǁA���قǓ��{�l�̔��ӎ��ɓK�����̂͂���܂���B���ʁA���̐l��f�킷�������͕|������߁A�×������̉��g������ɍʂ��Y���Ă��܂��B����ɂ�����̒m��Ƃ���ł͂Ȃ��A�����Ђ�����t�ɂȂ�ΉԂ��J���܂��B���NJJ�ԁB
�[ �� �� �P �� �� �� �� �� �� �i�ǎq�j
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �i�x�������j
�� �� �� �� �� �j �� �� �� �� �� �� �i���j
���n���� ��������� ���������� �s���t�� �тȂ肯�� �i�Í��a�̏W�j
�Ǔ� ��� �� �搶 �i09.04.23 �L�j
�@����18���A����� �搶������������܂����B�搶�͗ނ܂�Ȃ閾���ȓ��]�Ƒ��̒ǐ��������ʊw�����Ȃ��ă}���N�X�o�ϊw�ɑ傫�ȑ��Ղ��c����܂����B
���̊w���͐��̔_�ƌo�ϊw�Ɏ~�܂炸�F��o�ϊw�̒����Ƃ��Č��_�E�i�K�_�E���͂̑����ʂɋy�сA�Ȃ������ƓƐ莑�{��`�_����{�o�ϕ��͂͊m�ł���n�����߂Ă��܂��B
�搶�́A�ӔN�ɂ����Ă�����͌o�ϊw�S�W�̊�����ڎw�����̌��M�͐����邱�Ƃ�m��܂���ł����B�܂��搶�́A����̃G�b�Z�C�X�g�ł�����A���h���̒��ɂ������݂̂��镶�͂���I�܂����Đl���̃q���g��`�����ꂽ�悤�Ɋ��������̂ł��B
�t�[�����̌��A�ފ݂ɗ������ꂽ�搶�̂��⓿���ÂсA�S���炲���������F��\���グ�܂��B
�ʑ����� �i08.11.11 �L�j
�@����A�I����z�[���ŋv���Ԃ�ɋʑ�����̉��t���܂����B����̓p�������������y�@�����C���E�A�������Ƃ̃f���I���T�C�^���ł��B�ʑ�����̉��t�́A�����̗͋����̒��Ƀo�b�n�u�����t�p���e�B�[�^�v�Ŏ����ꂽ�[�����_������F���u�c�B�K�|�k�v�̉ؗ�ȋ|�g���͏\���ɒ��O�̐S���Ƃ炦���悤�ł��B
�@���̓��̈����̓x�[�g�[���F���u�N���C�c�F���v�ł����B���̃_�C�i�~�b�N�ŗ͊����鉉�t�́A�Ƃ����ӋC�����������ȍ����A�����ւ̌��C���v���[���g���Ė�����悤�Ɏv���܂����B
������l���{�l�̉��t�҂Ƃ��ď��҂��ꂽ ���C�v�c�B�q �u�o�b�n�t�F�X�e�B�o���v�ł̊����҂���܂��B�i09.03.16
�L�j
�@�O���l�L�҃N���u�ł̃R���T�[�g�ŁA�ʑ����o�b�n�̃V���R���k�����t���A���̑O�G����Ȃ�G������Ă��܂��܂����B�n�̔����|��f����W���͂̐��������邱�ƂȂ���A����Ȃ��������őO�ɂ��܂��ė͋����e�����������_�͂ɋ�������܂����B�S�Z�Ƃ��ɒ����ɐ������Ă���悤�ł��B
�����R �i08.11.13 �L�j
���{�̖��͂́A�l�G�܁X�Ɏ���قɂ���G�߂ƋN���ɕx�n�`�ɂ���܂��B���Ƀo���R�N�̂悤�ȁ@hot-hotter-hottest
�̐��E�ŕ�炷�Ƃ��̂��Ƃ��Ɋ��������܂��B�킪���̎��R�̔������͍����R�����ۓI�ȃK�C�h�u�b�N�Ɍf�ڂ����Ȃǐ��E�ɂ��m����悤�ɂȂ�܂����B�n�����g�������O����钆�A�㐢�Ɉ����p�������ő�̈�Y�ł��B
top page �ւ��ǂ�
|