�ς�O�͐�Ή������Ⴂ���Ă���Ǝv���Ă����̂����A���ꂵ����Z�ł������B���ɂ܂��Ƃ��Ȃł��̉f��ł���B�łт�m��R���A�C�����j�B�B�n�ӁA�^�c�̏���̔������B�T�����C�Łu�_���X�E�E�B�Y�E�E���u�Y�v�Ƃ����]���������Ė������A����܂ŃC���f�B�A���i�����I�ɐ������Ȃ��p��j�ȉ��������E�E�E�B��������u�L���E�r���v�Ŋ����������Ƃ�[�����Ȃ������̂ł������B
�Ƃ���ŁA�u�a���������{�v�ł����{�����ǂ����g�p����Ă��邪�A���{�l�̂��̕���ւ̈��A�ƌ������M�͍��[���B���j�����Ƃ̗�����Ǝ��́A�u�S�C�Ɠ��{�l�v�u���Ǝ���v�̗�����ŁA�����[���_�l�����Ă���B
���{���͌����ƍ���̍Œ��A�����Ȃ��Ȃ����G�̎���p�ɔ��B��������ŁA�퓬�Ɏg��ꂽ���Ƃ͂قƂ�ǖ����Ƃ����̂��i�������A���܂�ʂ��������͕ʂƂ��āj�B�퍑����̎����ŁA���ł̕����҂̌�������ׂ��Ƃ���A�|��S���A�S�C�Ƒ����Q�����A�c��Q�������̑��������Ƃ������ʂł������B�����ɂ������ẮA�S�̂̂V�p�[�Z���g�ɂ������A��U�߂̍ۂɓ��ŕ��������҂�菭�Ȃ����炢�������Ƃ����B�܂���{�̍���͐̂��牓������w���������̂ł���A���m���u��ѓ���͔ڋ��Ȃ�v�ȂǂƂ������_�������������Ƃ͈�x���Ȃ������̂ł���B
�܂��A���͈ӊO�ƌ̏Ⴕ�₷���B�����푈�̍ۂɌR���̏C���𐿂��������R���̏،��ɂ��ƁA���q�ƕ��̐ڑ����������������ɂȂ�̂��B���g�ƕ����ʁX�ɂȂ��Ă���̂́A�a������ۂ̏Ռ����z�����邽�߂̓��{���Ɠ��̍H�v�ł��邪�A���p��́A���܂ň�̐��`�̗m���̕����D��Ă���ƌ��킴��Ȃ��i�������A�g�p�҂̘r�O�ɂ��A�n���̏o���s�o���ɂ���邾�낤���j�B�������m�̍��Ȃǂƌ����o�����͕̂��a�ȍ]�ˎ���̂��Ƃł���A�ނ��Ɛl�������̓������ɉ��̖��ɂ������Ȃ������͎̂��m�̎����ł���B���̕ӂ̓p�I���E�}�b�c�@���[�m�u���Љ�w�̕s���Ȍ����v�ɏڂ����B
���`�Ƃ����̂��A��ɐ��܂ꂽ�T�O���B�����Ƃ����m�̊����퍑����͗����Ƃ̎���ł���A����̋A���͈�ɂ���ɂ��G����Q�Ԃ点�钲���ɂ������Ă����B�u�E���ȕ��m�v�Ƃ����̂́A�u�j�炵���J�E�{�[�C�v�Ƃ��u�����ȉp���a�m�v�Ƃ��Ɠ���̌��z�ɂ����Ȃ��B�����炭�A���������������z�̏W�ς��A�����Ƃ������Ƃ��`���Ƃ������̂Ȃ̂��낤�B�K���s�K���A�l�Ԃ́A�����Ȃ��ɂ̓A�C�f���e�B�e�B���\�z�ł��Ȃ��B�Љ���c��ł������߂ɁA�K�v�s���Ȃ��̂Ȃ̂��B
�������́A���ꂪ���z�ł��邱�Ƃɂ͎��o�I�ł��肽���A�Ǝv���B
���[�����C�i�f�O�T�D�R�D�P�O�j
�������Ă���̂͂悭�킩��̂����A���ꂾ���ɕs���������c��A�Ƃ����^�C�v�̉f��B�����Łi�f�扻��O��ɕ��s���ď����ꂽ�����Ȃ̂ŁA�u����v�ł͂���܂���A�O�̂��߁j�̈����B����ς�A�ڂ��C�ɂ����ɍ���̂͋����B���ǎ��Ԃ�����Ȃ��Ƃ����Ƃ���ɏW���̂����A�Ƃ肠��������Ƃ���Ȋ������B
�@�@�ɂT�O�V�̗����E�ٌ`�Ԃ�
�J�������Ȃ�p�������Ă��܂��̂ŁA����C���ɑ���a�C�������������͂Ƃ������قȎp���ǂꂾ���ُ�Ȃ��̂��A�쒆�ł̈�ۂ������B�܂��A�����Ŗ`���̃{�[���t�B�b�V���Ƃ̐킢�͌����Ă����ׂ��ł͂Ȃ��������B
�A�@��q�̐l����
�쓇�Ől����炢�A�S�ƂȂ��Đ��҂����j�̈�ۂ������B�Ȃ������Ɍ����𗎂Ƃ����悤�Ƃ��Ă���̂��A����ł͖��\�ȊC�R��]�ɕ��悤�Ƃ��Ă��邾���ɂ��������Ȃ��B���ӔC�̐���r���A���{�������Đ������邽�߂ɁA���{�l�̈˂��ė����̂����������Ă��s�����B�����Ȃ�̂͊o��̏�ŁA��q�̉����͕�������ׂ��������B�p�g�Q�݂����ȃX�}�[�g�ȕ��@���������͂��B
�B�@�����̊���
�A�Ɩ��ڂɊ֘A���邪�A�����̃o�b�N�O���E���h���`����Ȃ��̂ŁA�Ȃ���q�̌��t�ɋ��������ɂȂ�̂���������Ȃ��B�������܂��A���ӔC�̐��̔�Q�҂ł���A�����ɉ���l�ł��������Ƃ����_���d�v�Ȃ̂��B
�C�@�p�E���Ɛ܊}�̊W
�ȕv�ؑ��́A���̋Ɍ����ŗ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����|�̂��Ƃ������Ă������A�������낤���B�p�E�����A���̎����̒n�����甲���o���A�̘͂_������߂悤�Ɗo������߂邱�Ƃ��ł����̂͂Ȃ����A�������̂ł́B
�D�@���i�̖��Ӗ��Ȏ�
�����͂��̂̒�ԂƂ͂����A������ƁA���z�ȏ�ɊԔ��������B���݂����ɁA�{�[���𗣂��Ȃ�����肪�����܂���ł����A�ĂȃI�`���Ǝv�����B���������A�����łł͒��v����������q���u�i�[�o���v����̂��߂ɐ����v���Ɓu�C���v�����������Ă��킯�����A�f��ł͉��̂��߂ɏo�Ă����A�����B
�E�@�e�j�A�����C��
�쒀�͂����ljf�邾���ŁA�X�P�[���������B����Ȑ�͂��A��ꂪ�A�m������ɂ���Ƃ����G�ƁA�I�u���C�G���͒��̖����͐�ΕK�v�������͂��B
�F�@���X�g
���q�̎��͂�肷����������Ȃ����ǁA���[�����C�̔閧�𑒂邽�߁A��q�̊C��������ɂT�O�V�Ō�̍q�C�͌�����ׂ��������B
�����Ȃ��́A�S�Q�U�b���炢�ŁA�����ł̂Ƃ���A�j���������Ȃ��I�i�A�t�^�k�[���Ń}���K�ŘA�ڂ��Ă܂����A������ƂˁE�E�E�B�j
21g�i�f�O�S�D�U�D�T�j
�S���ڐA������R�l�̒j���̈������E�E�E�Ȃ̂����A������������āA�u�g�d�`�q�s�v�i�X�W�A�p�j�̃p�N���ł́H�@����ڐA�l�^�Ƃ����ƁA������������̈�@�����Ƃ����p�^�[���ɂȂ�̂����A���́u�g�d�`�q�s�v�́A������҂̓��̂����ꂽ���l�ւ̎����Ƃ��A�ٕ������ꂽ�����̓��̂ւ̋��|�Ƃ������ُ�S�����A�j���R�l�̈��~�Q�����n���G�}�̂Ȃ��ɕ`���o���ِF��ł���B���o�[�g�E�J�[���C���ƕ���ōŋ߂̃C�M���X�f��ɕK������o���A�������ςȖ�������̃N���X�g�t�@�[�E�G�N���X�g���i�l�Ă�ŃC�M���X�̑吙���j�Ƃ��A�T�X�L�A�E���[�u�X�̎v���l�߂��܂Ȃ����Ƃ��A�ٗl�Ȉ�ۂ��c���B�l����قǂɁu�Q�P���v�Ƃ�������B�u�g�d�`�q�s�v�̈̂��Ƃ���́A�l�ԃh���}�Ȃ�Ĉ����ȐF�C���o�����A�����܂ŃT�C�R�E�X�����[�Ƃ��ĕ`�������Ƃ��낤�B���ʂƂ��āAꡂ��ɐ[�݂̂���f��ɂȂ����B
�ŁA�u�Q�P���v�̕��Ȃ̂����A�V���[���E�y���A�x�j�`�I�E�f���E�g���A�i�I�~�E���b�c�Ƃ������Z������R�l�����ꂵ���M�����J��L����B���������āA���������f��͋�肾�B
�n���E�x���[���u�`���R���[�g�v�ŃI�X�J�[����������A�E�����藍���̓�����̔M���ƌ����̂́A���Ɍ��킹��A�I�͂���ł���B�u�`���R���[�g�v�̃n���E�x���[�̏ꍇ�A�^�ɕ]�����ׂ��́A�r���[�E�{�u�E�\�[���g���̔閧��m������A�����Ŕނ����߂�\��ł���B
�ЂƂ����A�u�Q�P���v�ɂ���ۓI�ȃV�[��������B�������o�čs���V���[���E�y�����A�J�������p�����Ēǂ��B�h�A���o������A�J�����͕s���R�ɐÎ~���Ă���B���̃J�������ʂ��Ă���̂́A������L�����L���X�g�̏������i���I�f�W���l�C���ɂ���A���̃~�j�`���A�j�B�����[�����ƂɁA���̃L���X�g���ɂ͖ډB�������Ă���̂��B�Ӗ�����Ƃ���͖������B�u�Ӗڂ̐_�v�ł���B���̐��̔ߌ������悤�Ƃ��Ȃ��_�B���ɗ����Ȃ��_�B����Ȃ��̂ɈӖ�������̂��H����Ȓ����I�ȃ��b�Z�[�W����������ƉB���Ă���B���ꂪ�A�f����ς�y���݂̈�ł���B
�C���E�U�E�x�b�h���[���i�f�O�Q�D�W�D�Q�O�j
�u���Ƃ��̃r�j�[�v�ŏ������D�܂�����Ĉȗ��A�������育�������̃}���T�E�g���C���ړ��ĂŊς��悤�Ȃ���Ȃ̂����A����͌���ł������B
�l�͂����ɂ��ĎE�l�҂ɂȂ�̂��B���ꂪ�A���̉f��̃e�[�}���B�}���T�E�g���C�̖��́A�\�͒���Ɨ������⒆�̐l�ȁB�ޏ��̗��l���A���i�ɋ���������ɎE�����B�^�̎�l���́A�E���ꂽ���l�̗��e���B�ނ��������̂��A�g���E�E�B���L���\���ƃV�V�[�E�X�y�C�Z�N�B�Ƃ�킯�A�E�B���L���\���̕��Â����\��Ɏ��܂̂�����a�́A���B�̋Z�B�\�͒���ƌ����Ȃ���A���͔ނ����ۂɖ\�͂��ӂ邤�V�[���́A��x���ʂ���Ȃ��i����ςĂ��Ȃ����A���̋L���ɂ��j�B�ڍׂ͏����Ȃ����A���̗��R���A���X�g�Ŗ��炩�ɂȂ�B
��ۓI�ȃV�[��������B�蓮�̊J�����B����A�}�W�ŁB�������߂Č����B���̐^�̋���Ƀo�[�������A������Ă��ƁA������]���Ă����āA�D���ʂ��悤�ɂȂ�̂ł���B���R���삷��҂́A��J�������邮�鑖���邱�ƂɂȂ�B�E�B���L���\�����A����߂Ă���B�K���ő���Ȃ���A�ǂ��ɂ��s���Ȃ��߈��B����͂܂�ŁA�ގ��g�̎p���B
�u��d���v���I�����ނ͖閾���ɋA��A�x�b�h�ɂ͂���B�Ȃ́A�����̂悤�ɔނ��}����B���X�g�J�b�g�́A�܂�ŕ�W�̌Q��̂悤�ȏZ��n�̕��i���B��l�Ƀx�b�h���[���̑����A������������Ă���B��l�̎��҂ƈ�l�̎E�l�҂�ŁA�����̂悤�ɒ�������B����͂܂������Ă����B�x�b�h���[���̐������A�閧������āB
�r�����̒��ق́u�f��I�v�\��
�T�C�R�E�X�����[�����̑c�i������c�́u�T�C�R�v('60)�j�B�͂����茾���āA���̃W�������̉f��͂��̂Q�{���ςĂ����Ώ\���ł���B��͂��D�݂Łu�Z�u���v('95)���炢���B�܂��u�Z�b�V�����X�v('01)�݂����ȉ�������邪�E�E�E�B�N�����X�E�X�^�[�����O�ƃ��N�^�[���m�ُ̈�Ȉ���������ɁA�A���E�l�S�o�b�t�@���[�E�r���Ƃ̑s��Ȑ킢��`�����{��B�X�g�[���[�≉�Z�ɂ��Ă͌��s�����ꂽ��������̂ŁA���̍�i�́u�f��I�v�\���ɂ��āA�G��Ă݂����B�u�f��I�v�ƌ����Ă���̂́A�f��ł����ł��Ȃ��\���A�Ƃ����قǂ̈Ӗ��Ŏg���Ă���B�Ԃ����Ⴏ�Č����Ă��܂��A�����ɐ����[���t�ɗ��炸�ɕ\���ł��邩�A�Ƃ������Ƃ��B�{��̖`���̃V�[���́A���̂���{�̂悤�Ȍ����ȕ\���ɂ��ӂ�Ă���B
�J���܂��A�u�o�[�W�j�A�B�N�����e�B�R�v�Ƃ����e���b�v���o�āA�����̐X���f�����B���փp������ƁA�}�ΖʂɃ��[�v�������Ă���A��l�̏��������[�v���悶�o���Ă���B���Ⓓ�̐��ɁA�ޏ��̍r�����Ɨ����t�݂����������d�Ȃ�B�X�̒���فX�Ƒ���ޏ����A�J�����͒ǂ�������B�ؘg�Ƀ��[�v�̒���ꂽ��Q����ޏ����o��n�߂�ƁA�J�����͏�Q������荞��ŁA�~��Ă���ޏ���҂ʒu�Ɉړ�����B�����̎��A�Ă���܂œo������ǂ�����̂��Ǝv�����B�����ŃJ��������~������A�������������܂ňێ����Ă����������������Ă��܂��B�ƁA�ޏ��͂ł�Ԃ��̗v�̂ŁA�����Ƃ����Ԃɏ�Q�����~���̂��B�������Ĕޏ��i�ƃJ�����j�́A����Ɏ����𑱂���B�R�[�X��̐ݔ��Ɣޏ��̐^���ȕ\��ɁA�����̌P���炵���A�Ƃ������Ƃ��킩��B�₪�Ĕޏ��͒N���ɌĂю~�߂��A����ƐÎ~����B�����������j���́A�ޏ��|�u�X�^�[�����O�P�����v���Ăяo�����Ă���A�ƍ�����B�ނ͂����ƃJ�����ɔw�������Ă��邪�A�X�^�[�����O��������`�ŃJ�����Ɍ�������B���̖X�q�ɑ发���ꂽ�e�a�h�̕����B�}�f�ȉ��o�Ȃ�A�u�e�a�h�A�J�f�~�[�v�̊Ŕ��ʂ�����A�e���b�v���o���Ă��܂����肷��Ƃ��낾�i�����Ƃ��A�N�����e�B�R�Ƃ����n���́A�e�a�h�A�J�f�~�[�̑��݂ŗL���ŁA�킩��l�͂��̒n�������ł킩��̂��Ƃ��j�B
�A�J�f�~�[�̌����ɖ߂����X�^�[�����O��ǂ��āA�J�����͌P�����B�̓���|���[�v���悶�o������A�e�𐴑|������|����ۂ悭�ʂ��Ă����B�Ƃ�킯���炵���̂́A�X�^�[�����O���G���x�[�^�ɏ��V�`���G�[�V�����B�G���x�[�^�ɏ�����Ƃ��́A�����͔ޏ���l�ŁA����͗D�ɓ���傫�������̒j�q�w�����肾�B�������A�X�^�[�����O�����W���[�W�Ȃ̂ɑ��āA�j�q�݂͂�Ȑ^���ԂȃW���[�W�ŁA�ޏ��̑��݂͔ۂ����ł��ڗ��B���̃J�b�g�ŃX�^�[�����O���G���x�[�^����~��Ă��邪�A���ɂ͒N������Ă��Ȃ��B
�����ŁA�Q�킩�邱�Ƃ�����B�ЂƂ́A�e�a�h�Ƃ����ǂ��A�����̌P�����͂܂����������݂ł���A�����炭�K�v�ȏ�ɔw�L�т��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ƁB���������A�����Ɉ�l�Ń����j���O�����Ă���l�q���A�����ɂ��ł���B�����ЂƂ́A�G���x�[�^����o�Ă����̂��ޏ������A�Ƃ����Ƃ��납�炷��ƁA�ޏ����Ăяo���ꂽ�̂��A���i�w�����o����ł��Ȃ��d�v�Z�N�V�������A�Ƃ������Ƃł���B�����ُ�Ȃ��Ƃ��n�܂�A�Ƃ������Ƃ������\��������B
�f����ς鑤�ɂ��A���ꂾ���̒��ӂƋْ���������{�삪�A����łȂ��킯���Ȃ��̂��B
�B�e�ē̓^�N�E�t�W���g�B���ׂĂ݂���A�W���i�T���E�f�~��i�ȊO�ɂ́A�V���}�����f��ɂ��悭�Q�����Ă���l�������B
�Ō�ɁA�]�k���̂P�B���́A�{�삪�A�J�f�~�[�܂���܂�����̊M�����o�C�o�������ŏ��߂Ċς��̂����A�u��肩����h�炷��v('01)�Ɠ�����f�ŁA���܂��ɏ������l�I�Ƃ������|�̑̌��ł����B
�]�k���̂Q�B�L���X�g�ɁA�uevangelist�v�Ƃ����𖼂��o�Ă���̂ʼn����Ǝv������A���N�^�[���m���������Ă���@���ԑg�̂s�u�`���t�������B
�f�O�X�D�T�D�Q�O�NjL
�쒆�̂�����ƋC�ɂȂ�\���B

�`���́A�P����Ɍf�����ꂽ�v���[�g�B�uAGONY(���)�v�uHURT(���)�v�uPAIN(��Y)�v�uLOVE-IT(���������)�v�Ɠǂ߂�B���͂��̉��B�����ꖇ�v���[�g�����邪�A����ēǂ߂Ȃ��B�����ɂ́uPRIDE�v�Ə�����Ă���悤���B
�Ȃ����̒P�ꂪ������A�������ǂ߂Ȃ��̂��H�{��̃^�C�g�����Î�����u�q�r���~���ҁv�Ƃ̓L���X�g�̂��Ƃł���A�܂��u�o�q�h�c�d�i�����j�v�Ƃ͂��������̑���̈�ł��邱�Ƃ��l����ƁA�Ȃɂ������̈Ӗ�������悤�Ɏv����B

���N�^�[���m�ƃX�^�[�����O�̍ŏ��̑ΖʃV�[���B���̃V�[���͗��҂̐�Ԃ��̃J�b�g���������A��ɃK���X�z���ɎB���Ă���i��̉f���ł͔����Ǝv�����A�{�҂��ς�Ɣ���j�B������P�̓s���ł͂��낤���A��ɑ���̎�σV���b�g�ł��邱�ƁA�Q�l�̊Ԃ����S�Ɋu�Ă��Ă��邱�Ƃ��������Ă�����B������A������x�w�悪�G�ꍇ���V�[���͊����I�Ȃ��̂ɂȂ�̂��B
�����P�C�ɂȂ�̂��A�u�������Ƃ������`�[�t�̑��p�v�ł���B��l���͖@�̎��s�A�܂�͍��ƌ��͂̑��ɐg��u���l�Ԃ�������邪�A��Ȃ��ƂɁA�ƍߎґ��ɂ����p�����̂��B

���N�^�[���m�̑ݑq�ɂ̒��ŁA�Ԃ��ށB���̒��ŃX�^�[�����O�͎��̂�����̂����A�u�����ɕ�܂ꂽ���v�ƌ����A�X�g���[�g�ɐ펀�҂�A�z������B

�o�b�t�@���[�E�r���̕����B���̌������̕ǂɐ��������\���Ă���B

�o�b�t�@���[�E�r�����ˎE�������ɔj��鑋�B���������͂���ō��ɓS�J�u�g�̂悤�ȖX�q�A�E�ɂ�G.I.�W���[�炵���l�`������B�o�b�t�@���[�E�r����N�^�[���܂��A�A�����J�̎Y�a�����Ƃ������ƂȂ̂��낤���B
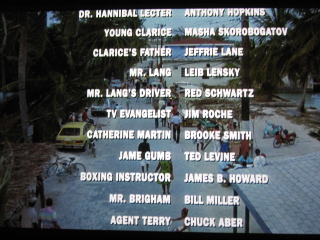
�G���h�N���W�b�g�B�`���g�����m��ǂ��āA���N�^�[���G���ɏ����Ă䂭�B
���̃V�[���A�Q�O�͂قڊF�i�ׂ��������ƑS���ł͂Ȃ����j����ʉ��֕�����A��x�Ɩ߂��Ă��Ȃ��B
�܂肱��́A�u�l�̎��ɍs�����v�Ȃ̂ł���B
����b�v���K�T���i�f�X�W�D�V�D�T�j
�������k���N���̉��b�f��B���ʂ̎���ɂ����J�����щ��тɂȂ��Ă����̂��A�{�M�����J�Ƃ����킯�ŁA�L�l�J��X�܂ōs���Ă��܂����B���ł������̖k�̎�̗l�͉��b�f��A���ɃS�W���V���[�Y�̑�t�@���Ȃ̂������ŁA�����ł��n�肽���A�ƍl�����B�����ł܂��A�؍�����X�^�b�t��U�����Ă����n�点���̂����A���܂�n��ӗ~�̂킩�Ȃ����������̂��o�����悭�Ȃ������i����A�\�����ǁj�B��͂�v���ɔC���Ȃ���_�����I�Ƃ����킯�ŁA�����ɓ��{����X�^�b�t�����ق��đn�����̂����́u�v���K�T���v�ł���B����������̃v���K�T���͒�����݂ŁA���ɓ����Ă���̂��A���^�����̃S�W�����ҁA�F�������Y�B
�v���K�T���́u�s���E�v�Ə����A������̖��b�ɓo�ꂷ��A�S��H�炤�s���g�̉����ł���B���b�͎����Ăق̂ڂ̂��Ă���A���㊯�ɋꂵ�߂���n�������l���A���R�E�����v���K�T���̗͂Ŕ������N�����A�Ƃ������́B�v���v�z�A�ƌ����Č����Ȃ����Ȃ��B�l���R�S�ʋ��͂̂��ɂ́A�}�X�Q�[�������킯�ł��Ȃ��A�X�P�[�����傫�������������悭�킩��Ȃ��B���Ղœo�ꂷ���̂Ђ�T�C�Y�̃v���K�T���́A�_�̐�ɐl�`�����t���đ����Ă���̂����������ŁA�قق��܂����B
�������A�v�����ʂ���������v���K�T���͂Ђ�����S������Đ����𑱂��A�l�X�͂��̑��݂����Ă��܂��悤�ɂȂ�A��l���̖��͉䂪�g��q���ăv���K�T����|���E�E�E�ƁA�Ȃ��Ȃ��V���A�X�Ȗ���B���̍��̑̐����v���ƁA���\���W�J���ȉf�悩������Ȃ��B
����ł́u�v���K�T�����`�v�ɋ߂������ŁA�ƂĂ����̔߂��������̖��ł���B
����ɂ��Ă��A���̂Ƃ����̕������P�W�O�O�~���A�k�̐l���̌��ƂȂ���ƂȂ�A�e�|�h���P���ƂȂ������{���щz���Ă������̂��Ǝv���ƁA���S�[�����̂�����B�[���A�E�Ɨϗ��ɂ��Ƃ邱�Ƃ����Ă��܂����悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B
�R�R�V���@�N�͍r����߂����i�`�x�b�g�ł͒��N���j�@�i�f�O�U�D�U�D�R�j
���̉f��̃p���t��ǂތ���A�z�����̃\�j�[�E�s�N�`���[�Y�́u��������Ă܂Ŏ�蔲�����Ƃ������R�̈̑傳�ƌ������v�u�_���^���A�c�悩��p�����厩�R�����̐���ֈ����p���ł��������v�݂����ȉf��Ƃ��Ĕ��낤�Ǝv���Ă����悤�ł���B
�����A���̉f��̓V�����e�E�V�l�Ȃł͂Ȃ��A�V�h���a�ق����J���ׂ��f��ł������B
�R�R�V���Ƃ́A�`�x�b�g�̍��R�n�т̂��Ƃ��w���B�W���S�V�O�O���A�قƂ�ǂ͐l�Ֆ����̒n���B
�X�O�N�㏉�߁A���̒n���ɐ�������`�x�b�g�J���V�J�́A�����Ȗє炪���邽�߁A���҂ɂ���ė��l���ꌃ�����Ă����B���̉f��́A���҂������܂閯�ԃp�g���[�����̐킢��`�������̂ł���B
�p�g���[�����Ƃ����Ă����Ԃ̂�����A�x�@�ł��R���ł��X�ьx�����ł��Ȃ��A�����܂Ń{�����e�B�A���B�u�����Ȃ��A�l����Ȃ��A�e���Ȃ��v�L�l�ŁA����ł��j�B�͎R���߂����B
�f��̎���̂ЂƂ́A�낭�ɑ����Ȃ��R�R�V���̍r�삾�B
������_�f�������̂ŁA���҂�ǂ��đ����������Ŏ_�����N�����A�|��Ă��܂��B
�Ԃ��X�^�b�N�����̂ŁA�������荻�n�ɏo��ƁA�����Ɉ��܂��B
���҂͖��҂ŁA�d�������Ă��邵�l���������̂ŁA�p�g���[����������Ɩⓚ���p�ōU�����Ă���B
���҂͖��@�҂����A�p�g���[�����̕��͂���ɗւ������Ė����ꒃ�ł���B
�_���̊��҂ɒ��˂��悤�Ƃ���ƁA�����̖��n���������Ȃ��B�ŁA�����āA���̌��ŗn�����B
�ߕ߂������҂�A��ĕ����Ă���ƐH�����R�����Ȃ�A�r���ŕ���o���B�u�R�O�O�L���قǕ����Γ��H�ɏo��v�ƌ����c���āB�i�l���ɁA�ł͂Ȃ��j
�\�Z������Ȃ����́A���ɂ��т�B���������є�𖧔����āA�����ɂ���B
����ł��j�B�͉Ƒ�����l�̗܂�U���A�R�R�V���������̂��B�u���Ȃ�����ł����邳�v�Ə��āB
���X�ɒ��Ԃ��|��A�Ԃ������Ă�����Ɍ������Ă��A�ǐՂ���߂Ȃ��B
�p�g���[�������є�𖧔�����̂́A��������Y�펖�������Ă����Ȃ�����Ȃ̂����A���ʁA�ނ炪���҂Ɠ������̃��W�i���A�Ƃ������Ƃł�����B�p�g���[�����͎��R�̂��߁A���҂͋��̂��߁A�Ƃ�������������ɂ͂��邪�A���ۂ͂���Ȃ��̂͂ǂ��ł������ɈႢ�Ȃ��B
�ނ�́A�ǂ�����ǂ�ꂽ��E������E���ꂽ�肷��̂��D���ł��܂�Ȃ��̂��B
�ނ�́A��n���҂��B�������A���Ƃ��悤���Ȃ������Ŕ������n���҂ł���B
���̂Ȃ��ɂ��A�ނ�������܂����v���C�������m���ɂ���B�����ɂ��������������قǂ̋C�T���̗͂��Ȃ��̂ŁA�����ĉf����ςĂ���B
�ȉ��͎֑��B�f��̖`���ŁA�}�E���������̑��V������̂����A�`�x�b�g�����璹���ł���B
�ŁA�������āA��̂��i�^�ŁE�E�E�܂肻�́A�u�H�ׂ₷���v����̂ł��ȁB�m��Ȃ�������B
�R�[�G���Z��̉f�����p
���E��̉f��̌���ƌ����A�R�[�G���Z���u���đ��ɂȂ��B�ނ�̉f��́A�Ƃɂ����Z���t������ɗ���Ȃ��B�f�����ςĂ��邾���ŁA���ł��`�����邵�A�`���Ă��Ƃ����C�����قƂ����Ă���B
������́u�u���b�h�E�V���v���v�����ɂ����������B�����T�オ�A�o�[�o�c�҂���ȂƊԒj���E���悤�˗������B�T��͎E���̏؋��ʐ^�������ĕ�V�����B���̃V�[���ŁA�T��͎ʐ^��R�₵�Ă���B���̎ʐ^�́A�؋��ʐ^�̃o�[�W�����Ⴂ�B�܂�A�����Ȃ̂��B���̃V�[�������ŁA����点�Ă��܂��B
�@���W���[������́u�����͍��v�ł́A�t���t�[�v��q�b�g�܂ł̃V�[�N�G���X���ς�Ώ\�����낤�B����Ȃ��t���t�[�v���ǂ�ǂ�l��������A�₪�ĕ��𗧂Ă��������ቮ�̓X�傪���[�ɕ���o���B���̂����̈�{�����H�𑖂��Ă����A��l�̏��N�̑O�Ŏ~�܂�B�ނ͂�����E���A�{�\�̂܂܂ɉn�߂�B�܂������ی�ŁA�w�Z����o�Ă����q���B�������ڂɂ���B���݂Ƀt���t�[�v�����N�Ɍ��Ƃ��q���B�B�ނ�́A��C�ɂ������ቮ�ɑ���B�ǂ�ǂ�l�オ�肵�Ă����t���t�[�v�B����Ő��E�I�u�[���̏o���オ��A�ł���B
�@�����āA�ō�����́u�t�@�[�S�v���B��l���́A�������̋`������������܂���邽�߁A�Ȃ̋U���U������Ă�B������A�O�o����A��ƉƂ��r�炳��Ă���B�������ق����Ɛl���Ȃ�U�������̂��B��l������藐���ċ`���ɓd�b�������鐺����������E�E�E�Ǝv������A�ނ͓d�b��������O�ɁA�`���ɘb�����e�̗��K�����Ă����̂ł���B����قǁA�i���Ƃ������̂�N�₩�ɕ`�ʂ����V�[�����������낤���B
�₪�āA��l�����s���͂��������g����̎�茻��ɁA�`���������ɏo�����Ă��܂��B�����āA���_�̖��ɔƐl�ɎˎE�����B�S�z�Ō��ǂ��Ă�����l���́A�Ԃ̃��C�g�ɏƂ炳�ꂽ�`���̎��̂�������B�����Ȃ̂͂��̌�̃V�[�����B�Ԃ̃g�����N���J���̂��ʂ������Ȃ̂ł���B���ꂾ���ŁA���̂��B���C�Ȃ̂��ȁA�Ɣ��点�Ă��܂��B�����[���t�̑����}�S�̉f��ḗA�ނ�̒܂̍C�ł������Ĉ��ނׂ��ł���B�Ƃ���ŁA�`���ɂ��̍�i�͎��b�����ɂ��Ă���ƃe���b�v���o�邪�A�K�[�X�����搶�ɂ��ƁA����ɊY������悤�Ȏ����͌�������Ȃ��Ƃ����B�܂�A�ŏ�����z���Ȃ̂��B�������Ƃ��������E�E�E�B
�������A�ǂ������̌�p�b�Ƃ��Ȃ��B�u�r�b�O�E���{�E�X�L�v�ɂ��Ă��炪���ɂ͂ǂ����ʔ����̂������ς蔻��Ȃ��������A�u�I�[�E�u���U�[�I�v�u�o�[�o�[�v���Z���t�p���f�B�̂悤�������B�W���[�W�E�N���[�j�[�ƃL���T�����E�[�^�E�W���[���Y�̂Q��X�^�[�𓊓������u�f�B�{�[�X�E�V���E�v�ŏ����������������̂́A�u���f�B�E�L���[�Y�v�͂��͂�s�����ȃ��x���������B
���v���H
�����@�i�f�O�U�D�V�D�W�j
�u�փC�`�S�v('02)�̐�����a�ē̐V��B�O��̃u���b�N�R���f�B�����͉e����߁A�l�Ԃ̓��ʂɐ[�����ݍ��A����X�g���[�g�����ł���B�����Ŏʐ^�ƂƂ��Đ������Ă����i�I�_�M���W���[�j�ƁA�c�ɂʼnƋƂ��p�����Z�i����ƔV�j�B��̈�����ŋv���Ԃ�ɍĉ���Q�l�́A�c�Ȃ��݂̏��̎q�Ƌ߂��̌k�J�ɗV�тɍs�����B�ޏ��́A�Z�̋ߐ�̃o�C�g�����A���͒�Ɛ[���W�ɂ���B�k�J�Ŋy�������Ԃ��߂����̂����̊ԁA�k���ɉ˂������݂苴����ޏ����]�����A�M������B���̏�Ɉꏏ�ɂ����̂͌Z�����B���̂��A����Ƃ��E�l���H
�Z�ɎE�l�e�^��������A��͍ٔ��̂��߂ɖz�����邪�A�u�����Ȃ����l�v�ł����Ȃ������Z�́A����ɒ�̒m��Ȃ���ʂ������n�߂�|�B
���̂Ƃ���A�\���҂����ς������ŁA�قƂ�Ǘ\���m���Ȃ��Ŋς��B�Z��̏���݂̂����Ȃ��Ǝv���Ă����̂����A�ǂ����āA�~�X�e���[�Ƃ��Ă��S���T�X�y���X�Ƃ��Ă��ꋉ�i�ł������B��{�I�ɂ͎����̉�b���Ȃ̂����A�������܂��ꂽ�䎌�̂ЂƂЂƂ��ƂĂ��Ȃ��ْ����͂�ށB�c�ɂł����Ȃ������𑗂��Ă���Z���A���S�����B���Ă������i����݁B�킪�A�Z�ɑ��ĕ����Ă�����߂����ƁA����Ɨ����́u�����l�v�߂���Z�ւ̂��炾���B����炪���X�ɘI��ɂȂ�A�Ԃ����Ă����B�����ĖK��闠��ƁA�~�ρB
��ʐv�ɂ��A�H�v������B�Z�ƒ�́A��Ɂu�����瑤�v�Ɓu�����瑤�v�Ɉʒu���Ă���̂ł���B�H��ł́A���������킹�ɍ���B��x���A���Ă�����ɐ���������Z�́A��������B��͘L���ɗ������܂ܕԎ�������B�k�J�������Ԃ̂Ȃ��́A�O�Ȃƌ�ȁB�킪�Z������̂́A���[���~���[�z���ł���B�k�J�ɂ��Ă�����A�Z�͐�̂Ȃ��A��͊ݕӁB���邢�́A����ɂ͂�����Ɛ���u�ĂĔފ݂ƍ��݁B�Z�����Ă���Ă���́A�ʉ�̃K���X�z���ł��邪�A�R��ڂ̖ʉ�ɒ��ڂ������B�Q��ڂ̖ʉ�܂ł́A�݂��̃o�X�g�V���b�g�̐�Ԃ��Ƃ����펯�I�ȍ\�}���A������̂����A�R��ڂ̓K���X�𒆉��ɂ������f�ʐ}�ŁA�Z�킪�V�����g���[�ɔz�u�����̂��B���̂R��ڂ̖ʉ�ŁA�Z�͒�ɁA�u�ŏ�����l���^���āA��x����Ƃ��M�����肵�Ȃ��B���ꂪ�A���̒m���Ă��邨�O����v�Ɨ⍓�ȑ䎌�𗁂т���B�����ƒ�Ɏ����𒍂��ł������̂悤�Ɍ�����Z�́A�ނ��o���̈��ӂł���B���̂Ƃ��A�Q�l�̗͊W�͊��S�ɝh�R���Ă���B���ꂪ�A�\�}�ɂ��\������Ă���킯���B�����āA���X�g�V�[���B��͂�Q�l�́A���H������ł�����Ƃ�����ɂ���B�u�ƂɋA�낤�I�v�Ƌ��Ԓ�ƁA����ɋC�Â��݂��ׂ�Z�B�A��ׂ��ƂƂ́A���Ȃ̂��B�ǂ��ɂ���̂��B���������A����Ȃ��̂͂������̂��B����Ȃ��Ƃ��v�킹�A�t���[���C�����Ă����o�X���Q�l�̊Ԃ�f����B
�����Q�J�������̗�O���A�݂苴�̏�̃V�`���G�[�V�����ƁA��̌`�������Ōk�J�̋L�^�t�B������������V�[���ł���B���̌k�J�̎v���o���A�Q�l���Ȃ��ł���Ƃ������ړI�Ȕ�g�ł��낤�B
�I�_�M���W���[�́A���́u�A�J���C�~���C�v('02)�Ō�������ŁA���̂Ƃ��͓�����Ɛ�쒉�M�Ƃ����������݂����Ȗ��҂ɋ��܂�āA�ɓO�������Z�������̂����A����͂��̑��݊���S�J�ɂ��Ă���B����ƔV���āA�܂��S�P�˂������̂��B���̐悪�y���݁B�N��Ƃ����A����ē͂V�S�N���܂���Ă��Ƃ́A�܂��R�Q�ˁI�I�������Ⴂ����Ȃ����I�e���ł́A�������炵�����@�����������ؑ��S�ꂪ�o�F�B�u�փC�`�S�v�̋{�����V���������������A����ē͂��������������ʍ\���̖��҂@����̂��A���ɂ��܂��B���łɁA���{�l�͏��D�ł�����Ă��������Ȕ��l�ł���B�����ɂ����A���ꂩ��R�C�S�O�N�͌����Ŋ���ł���͂��B�M��E�́A���ꂩ����ɖL���Ȏ�����}����B
���z�i�f�O�U�D�X�D�Q�R�j
���̓��ʂ̌v��m��Ȃ��A�Ƃ����_�ɂ����āA����j�Ɏ��݂����l���Ƃ��Ă͍ő�̓���ł��낤���a�V�c���A�C�b�Z�[���`���܂������ꐢ���̖����ʼn�����B�C�b�Z�[���`���N�p�������R�͕s�������A���̑z���ł́A�u��l�ŋ��̑��l�ҁv�ł��邱�Ƃ����ߎ肾�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���B
�f�ГI�ȋL�^����I�������炷��ƁA���a�V�c�́A���j�̐ߖڂ��Ƃɂ����Ƃ����m�ȏ���f�������Ă��Ȃ���A���̈ӎu������ɔ��f���ꂽ�̂́A�|�c�_���錾����́u���f�v�����������B���l�_�Ƃ��Ĉꍑ�Ƃ̉^����S���Ȃ���A���̔j�ł�H���~�߂��Ȃ������䂳�B����̓M���V���_�b�̗\���҃J�T���h���̂��Ƃ��A�܂�ň�l�ŋ��̂悤�Ȃ��̂������낤�B������A������ǂ��납�ϋq�������Ȃ���l�ŋ��ł���B�C�b�Z�[���`�ɂƂ��āA���̋��|�Ɛ�]�͐g�ɔ�����̂ł������낤���Ƃ́A�z���ɓ�Ȃ��B
�i����̑����Ƃ���Ȃ̂ŏ����Ă������A�������@���̓V�c�͗����N��ł���A�ӔC���{�̌���������͂Ȃ������B�܂��A�V�c�̈ӎu�����f����Ȃ������̂́A�������ꂽ�̂ł��ȉ����ꂽ�̂ł��Ȃ��A�P�ɍ����O�̏������������Ȃ����������ł���B�j
�悭���T�[�`���ꂽ�f��ł���B���a�V�c����O��c�Ŗ����V�c�̌䐻���Љ��̂́A���ĊJ������肵����O��c�Ŏ��ۂɂ������G�s�\�[�h�B�J��̉�����r���ږ��@�ɋ��߂�̂́A�u���a�V�c�Ɣ��^�v�̋L�q�B�u�l�Ԑ錾�v�̘^���Z�t�����������A�Ƃ����G�s�\�[�h�́A�j�����ǂ������͒m��Ȃ����A�O���R�I�v�̍Ŋ���A�z������B
���̉f�������Â���̂́A���ƌ��ł���B
�{��́A�S�҃m�C�Y�ɖ����Ă���B��s�@�̔����A���̐��A���̐��A���v�̉��B����͂܂�ŁA�_�ɂƂ��Ă͐l�̐������̐����A�S�ē����Ȃ��̂ł��邩�̂悤���B
�܂��A�^�C�g�����u���z�v�ł���Ȃ���A���z�Ɛ�͌����ĉf��Ȃ��B
����͒n���h�̉�c���ł���A��̔p�Ђł���A���E�\�N�ɏƂ炳�ꂽ�f�g�p�i�ߊ����ł���A��Ɉłɕ�����Ă���B�ʐ^�B�e�⌤�����̖��邢�V�[���ł����A�����͂ǂ��ɂ���̂����炸�A����Ȃ��������邾�����B
�l�Ԑ錾���o�āA���X�g�V�[���ɏ��߂āA���ł̒��̑��z���f��B�l�ł���_�ł���A�V�c�͂��̍��̏�ɏ_�炩�Ȍ��𑗂葱���Ă���B
�P���l�̂��߂̃\�i�^�i�f�O�V�D�Q�D�Q�S�j
�茳�ɁA�u�O�b�o�C�E���[�j���I�v���ς��Ƃ��̃���������B���傤�ǂR�N�O�ɂȂ邪�A�u���������z���Ƃւ̃��N�C�G���B�Ƃ͌����A���h�C�c���ăm�X�^���W�b�N�Ɏv���Ԃ��鍑�Ȃ낤���B�x�@���Ƃ̋��|�ƕǂ��`����Ȃ��̂��������C�ɂȂ�B�v�Ə����Ă���B
�u�O�b�o�C�E���[�j���v�͌���ł͂��邪�A�u����Ă��Ȃ������v�̑�����i�������B
���́u����Ȃ����������v��������̂��A���́u�P���l�̂��߂̃\�i�^�v�ł���B
�h�C�c���勤�a���B�u�\�A�ȏ�ɎЉ��`�I�ȍ��v�ƌ���ꂽ���B
���̎Љ�̐����x�����̂��A�閧�x�@�u�V���^�[�W�v�ɂ��A�O�ꂵ�������̊Ď��Ɩ����̏���ł���B�h�C�c�����̏����J�ɂ���āA�אl��e�Z��A�Ƃ��ɂ͔z��҂��������҂ł��������Ƃ����炩�ɂȂ�A�[���Ȑl�ԕs�M����m�C���[�[�ɂȂ�҂����������Ƃ������B
���̎��ԂɎa�荞�̂��A���̉f��ł���B�G��Ȃ̂́A�Ď�����V���^�[�W���̐l�Ԃ���l���ɐ��������Ƃ��B��l�����B�[�X���[��т́A�x�e�����̃V���^�[�W�E���ŁA�q��̃v���B���Y�}�̋����𒉎��Ɏ���Ă��邪�A�ʒi���M�I�ł��G�L�Z���g���b�N�ł��A�c�s�Ȑl�Ԃł��Ȃ��B�����A�^����ꂽ�E����W�X�Ƃ��Ȃ��Ă��邾�����B���Ƃ����ꂪ���⓯�R�̐q��ł����Ă��B
���̗�Â��ɂ����A�^�̋��|������B�ΕׁA�����A�ӔC���B�E�Ɛl�Ƃ��Ė{�������ł���͂��̂����̎������A��l���I�ȊĎ����Ƃ��x���Ă����B
���鎞�A���̐��̋^���̂��錀��ƂƂ��̗��l�̊Ď��C���ɏA�������ƂŁA���B�[�X���[�̓��ʂɕω���������B
���w�B�����B���y�B���R�B���B
���B�[�X���[��������E�����b�q�E�~���[�G�́A�Z���t�����Ȃ���Ε\����قƂ�Ǔ����Ȃ��̂ɁA�K���X�ʂ̂悤�ȓ��ŁA���̐S�̂����g�������ɕ\�����Ă���B
����Ƃ́A�����̎G���ɓ��Ƃ̎x�z�̐��̍����L�����A���B�[�X���[������������������ƂŁA�ߌ����K���B���̉ʂĂɂ���A�킸���ȋ~�ρB
���̉f��̕���́A�P�X�W�S�N�ł���B�����Ƃ��날�܂�G����Ă��Ȃ��悤�����A����͂����炭�W���[�W�E�I�[�E�F���ւ̃I�}�[�W���ł���B�I�[�E�F�������悻�U�O�N�O�ɗ\���������́A�m���ɂ��̂Ƃ��A���̒n��Ɏ��݂����B
���n��V���b�t���f��
���n���O�コ�����\���̉f��ނ��Ă݂��B
���n��V���b�t���f��Ƃ����p��͎����K���ɍ�������̂ł��邪�A�쒆�Ŏ��n����ւ���Ă��邱�Ƃ������̉f��A�Ƃ�邭��`����B
�������A�P�ɖ{�Ғ��ɉ�z�V�[��������f��A�{�҂���z�ō\�����ꂽ�u�����v�̉f��i��F�u�X�^���h�E�o�C�E�~�[�v�j�͊܂܂Ȃ����̂Ƃ���B
�P�@���c�q�^