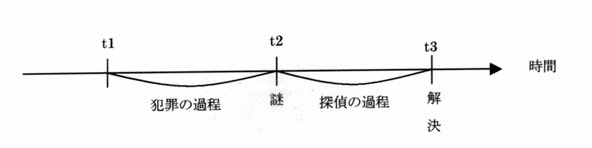|
犯罪と探偵――「陰獣」 論 真田啓介
1 緒 論 「陰獣」 をいわゆる変格探偵小説として読むか、本格探偵小説と見るかは、読者の趣味嗜好という以上に、探偵小説に対する基本的な認識如何の問題である。 「陰獣」 変格説の根拠となりうるような要素が、この作品中に相当多量に含まれていることは事実である。冒頭の博物館の場面ですでに読者は、本篇のヒロイン、「さわれば消えて行くかと思われる風情」 の美しい女性小山田静子の項(うなじ)に、「おそらく背中の方まで深く、赤痣のようなミミズ脹れができていた」 ことを知らされ、物語の展開に何事かを予期せずにはいられない。やがて静子から明される探偵作家大江春泥の邪悪な復讐計画。その春泥が浅草公園でとんがり帽と道化服をつけて立っていたという、雑誌記者本田の異様な報告。小山田邸の天井から聞こえてきた 「屋根裏の散歩者」 の時計の音。ミミズ脹れの意味を告げる鞭の発見。静子と寒川のただれた愛欲の日々……。 それらの印象的なディテールに加えて、「陰獣」 というこのタイトル。『探偵小説四十年』 によれば、「元来は 「陰気なけだもの」 という意味だったのが、セクシュアルな連想から 「淫獣」 というような語感を持ちはじめ、変態的な犯罪があると、新聞の見出しに 「陰獣」 という大活字が屡々現われるようになった」 という。後年の通俗スリラー長篇 『盲獣』 のイメージなどとも通じるところのあるこのタイトル自体が、この作品の変格的要素を代表しているようにも見える。 しかし、それらの要素にのみ目を奪われてこの作品を変格ものに分類するとすれば、探偵小説としての 「陰獣」 を読んだことにはならぬであろう。何が書かれているかは、二義的なことである。重要なのは、それがどのように書かれているかである。「陰獣」 には上にあげたような変格的要素を圧倒して全篇に横溢している論理的興味があり、これは伏線の配置の妙、構成の必然といった探偵小説に特有の技巧の成果である。「陰獣」 は必ずしも本格ものの常套形式をふんではいないが、その本質的要素である論理的興味が全篇を支配している点において、まぎれもない本格探偵小説であり、それ以外の何ものでもない。 作者自身も、「「陰獣」 は変態心理の部分が目立つので、純探偵小説といえないという見方もあるが、私自身はあれを本格ものと考えている」 と述べている (『探偵小説四十年』)。また、昭和10年に柳香書院から出版された作品集 『石榴』 には、「石榴」、「陰獣」、「心理試験」 の3篇が収められているが、これは作者がこの3作を自分の純探偵小説の代表的なものと考えたからであった (同書)。 本稿は、「陰獣」 の本格探偵小説としての技巧を、その論理的興味を中心に分析しようとするものである。 2 井上良夫の 「「陰獣」 吟味」 「陰獣」 の本格的興味については、すでに井上良夫がすぐれた論文を物している。その 「「陰獣」 吟味」 は、「ぷろふいる」 昭和9年8月号に、連載評論 〈傑作探偵小説吟味〉 の第2回として発表されたものである。このシリーズは、クリスティ 『アクロイド殺し』、ルルウ 『黄色の部屋』、クロフツ 『樽』 といった世界ベスト級の作品を論評したもので、「陰獣」 をこれらと同列に扱った井上の態度は乱歩を喜ばせた (「陰獣」 の発表は昭和3年だから、時評的な意味で取り上げられたわけではない)。この井上の評論は 「陰獣」 の本格探偵小説としての技巧について委曲を尽くした分析を行っているので、本稿の論を進める前にその論旨を概観しておくこととする。 井上はまず 「元来乱歩氏の作品には、厳正な意味での探偵小説は少いが、「陰獣」 は立派な本格探偵小説である」 とし、自分は一般にもてはやされている濃厚な色彩においての乱歩の作は好きでないが、「陰獣」 はそうした乱歩趣味が濃厚である反面、本格ものの真髄を把持しているところからくる独特のうまさがはっきり出ている点で愛読する作品であると述べている。 その乱歩独特のうまさとして第一にあげているのは、「探偵小説的サスペンス」 を盛り上げるテクニックである。
そして、このような効果をもたらすテクニックを、次のように分析している。
まことに鋭い分析であり、論者の的確な批評眼を感じさせる一節である。このように作者の手のうちまでも読み取ることができたのは、井上自身が本格探偵小説の魅力とその本質を充分に体得していたからであろう。 続いて、一人三役という非現実的なトリックをうまく扱いこなしており、真相説明の箇所において読者を充分に納得せしめている点を賞賛している。
そして、その論理的興味は 「真相説明」 の箇所だけではなく、全篇にわたっていわゆる乱歩趣味を圧倒的に打ち負かしていると述べている。 一方、この作の弱点としては、骨組みの貧弱さをあげている。
この点については、乱歩は必ずしも承服しない旨 『探偵小説四十年』 で述べている。
しかし、この文章は井上の没後に書かれたので、議論の進展は見られなかった。 「「陰獣」 吟味」 の論旨は大略以上のようなものであるが、探偵小説の作品論として充実し、また行き届いた内容をもった力作であるといえる。昨今横行する感覚だけを頼りにした印象批評的な作品論とは異なり、ここには探偵小説の本質への洞察をふまえた、論理による冷静な批評が見られる。乱歩の 「本陣殺人事件を評す」、「不連続殺人事件を評す」 などと並んで、探偵小説作品論のすぐれた実例として記憶されるべきであろう。 だが、「「陰獣」 吟味」 においては、その 「探偵小説的サスペンス」 をもたらす技巧についてはふれられていたが、論理的興味の内容については必ずしも充分な分析がなされていなかった。以下においてはその点を中心に、「陰獣」 の本格的興味について考えてみたいと思う。
(1) 二種類の論理 「陰獣」 の論理的興味を分析するにあたって、まずその論理の絵模様ともいうべき全体の構図をとらえるために、一つの視点を設定しておきたい。すなわち、「陰獣」 においては、探偵小説の論理的興味を形成する二種類の論理が、他に類を見ないほど緊密に――絡み合った二匹の蛇のような図柄を呈しながら――結び合わされているのである。その二種類の論理とは、犯罪の論理と探偵の論理である。 「陰獣」 は、次のような随筆風の書出しで始められている。
この探偵作家の傾向分類は、大正15年 「新青年」 春の増刊に掲載された平林初之輔の 「探偵小説壇の諸傾向」 における不健全派・健全派の分類に基づくものと考えられ、その後一般化した変格派・本格派の分類とも対応するものである。この分類は、表面的には探偵作家の作風による区別にすぎないが、この二人の探偵作家を変格探偵小説そのものと本格探偵小説そのものになぞらえることもできるし、また、一般に探偵小説における犯罪的要素と探偵的要素を代表するものと見ることも可能であろう。より端的にいえば、犯罪と探偵――探偵小説を構成する二大要素である。 この二大要素を論理的興味という側面から眺めてみれば、そこに犯罪の論理と探偵の論理という二種類の論理が抽出される。 探偵小説における論理を作中探偵の推理の部分にのみ局限してとらえる読者には、「犯罪の論理」 といった概念は意味をつかみにくいかもしれないが、要するに犯罪者の側の論理のことをいうのである。ある状況のもとにある犯罪の動機が形成され、その動機に基づいてある犯行方法が選択され、犯罪が遂行されるに至る、その一連の過程。そこには、動機を出発点とする演繹的な論理展開が見られる筈である。その論理は作品の表面には現れないで、いわば影のプロットとでもいうべきものを形成する。犯人の用いるトリックは、犯人によって選び取られた犯行手段を構成する要素であり、犯罪の論理の流れの中に位置づけられる。この犯罪の論理は、通常、その結果である犯罪が冒頭において提示されるだけで、結末に至るまでその全貌を現さない。 この犯罪の論理と対決し、それを発こうとするのが探偵の論理である。ここで探偵というのは探偵行為 (detection) の謂であるが、それは多く作中探偵 (detective) によって代表される。探偵は犯罪結果を調査して手がかりを拾い集め、その結果がどのようにしてもたらされたかを探ろうとする。探偵の論理は、演繹的に自己展開する犯罪の論理に対して、帰納的な論理であるといえる。 (2) 一般に本格探偵小説の構成について 本格探偵小説においては、冒頭に提示された犯罪事件の謎をめぐって作中探偵が調査を行い、結末においてその謎を解決する。謎とその解決というのが基本的なパターンである。表面的なストーリーは探偵の調査とともに進行していくから、論理として目につくのは探偵のそれだけであり、〈名探偵の推理〉 がすなわち探偵小説における論理であり、それのみが探偵小説の論理的興味を形造るものであると考えられやすい。 しかし、それは誤りである。探偵の論理が成立するためには、その前提として犯罪の論理が存在していなければならない。探偵の論理が向かう謎=犯罪結果をもたらすものこそ犯罪の論理である。解決があくまで謎に対する解決であるように、探偵は犯罪に対する探偵なのである。すなわち、謎と解決は犯罪と探偵に対応する。 本格探偵小説における論理的興味は、このように犯罪の論理と探偵の論理の二つの要素から構成されているのであるが、犯罪の論理は読者の論理的興味の視野に入ってこないことが多い。これは本格探偵小説の特殊な叙述形式によるものであろう。すなわち、本格探偵小説は、結果から始まって原因を探究する物語である。そこでは時間的な順序が逆転しているのである。
上の図によって説明すれば、t1からt3へと進行していく時間軸の上で、まずt1時に成立した犯罪の論理――多くは動機の成立と対応する――は、演繹的な自己展開を遂げて、t2時においてその結果をもたらす。つまり、犯罪が具体的に実行される。ここで既に物語は一つの段階を終了しているのであるが、探偵小説はここから始まる。実行された犯罪の結果が提示されて、冒頭の謎を形成する。探偵の過程はストーリーの進行と対応し、手がかりが出そろったあと、t3時において「謎解き」 が行われる。探偵の論理によって、犯罪の論理が発かれるのである。 もちろん、実際には犯罪の過程と探偵の過程はt2時といった特定の時点で判然と区分されるものではなく、両者が重なり合う部分も多い。たとえば連続殺人事件の場合などには、犯罪の論理と探偵の論理の追いかけっこのような形になるし、探偵行為自体が新たな犯罪の動機になる例も少なくない。しかし、基本的なパターンは上記のようなものである。 この間の事情は、倒叙探偵小説の場合と比べてみると、より明瞭になる。倒叙探偵小説は、さかさまに書かれた探偵小説であるといわれる。犯人は冒頭から登場するのである。しかし、これを先の図の時間軸にのせてみるとどうなるか。物語はt1時に始まり、t2時を経過してt3時に終わる。ごくあたりまえの、時間の流れに沿った物語の進行である。どこが 「さかさま」 なのか。倒叙探偵小説は正叙小説なのであって、このことは、(倒叙でない一般の) 探偵小説こそがさかさまに書かれた物語であることを教えるのである。すなわち、探偵小説においては、犯罪の論理と探偵の論理の登場の順序が、実際の時間の流れにおけるとは逆になっているのである。 以上のことからして、犯罪の論理が探偵の論理の陰に隠れがちな理由は明らかであろう。探偵小説のストーリーはt2時からt3時の間に進行していくものであるから、表面に現れるのは探偵の論理だけなのである。犯罪の論理は、探偵の論理の前提になるものではあるが、実際に作品に姿を現すのは結末の謎解きの場面においてでしかない。t1時からt2時にかけて展開した論理がt3時に一挙に語られるのであるから、往々にしてそれは駆け足の、断片的なものになりがちである。それを嫌って犯罪の論理に充分なスペースを与えようとすれば、倒叙探偵小説の形をとるか、コナン・ドイルの 『緋色の研究』 のようなスタイルをとらざるを得ない。『緋色の研究』 の第二部は、先の図でいうt1時からt2時までの物語である。 このように、一般の本格探偵小説においては、犯罪の論理は結末においてやっと表面化するのであり、探偵の論理も多くは結末において集中的に展開される。その前には、多かれ少なかれ退屈なお膳立てが必要なのである。 (3) 「陰獣」 の場合 「陰獣」 における論理的興味の特殊性は、犯罪の論理と探偵の論理が結末において初めて表面化するのではなく、両者互いに拮抗しながら全篇を通じて表に現れている点にある。この二種類の論理が――別の言い方をすれば犯罪的要素と探偵的要素、〈変格〉 と 〈本格〉 とがこのような仕方で結び合わされた作品というのは、他に類を見ないのではあるまいか。「陰獣」 が分量的には中篇ながら、その読後感が充分長篇のそれに匹敵するのは、この探偵小説に本質的な二要素が全篇を支配しており、一部のムダ、スキ、遊びもないからではないかと思われる。二種類の論理の絡み合いの様相を、以下具体的にたどってみよう。 物語は、〈探偵型〉 の探偵作家である 「私」 =寒川と小山田静子の出会いから始まる。静子が寒川に打ち明けたところでは、〈犯罪者型〉 の探偵作家大江春泥が、昔の恋の復讐のために静子に脅迫の手紙を送ってきたというのだ。犯罪の論理と探偵の論理が、大江春泥と寒川の対決という形で具体化されることになる。 春泥から次々に届く手紙には、人に知られるはずのない静子の行動が克明に記録されていた。春泥は、自作 「屋根裏の遊戯」 を実行に移したものらしかった。寒川が屋根裏に上がってみると、そこにボタンが落ちていた。――犯罪行為とそれに対する探偵行為がそれぞれ進行を始める。 やがて静子の夫、小山田六郎の変死事件が起こる。春泥の仕業か? 天井裏に落ちていたボタンが小山田氏の手袋についていたものだったことなどから、寒川は、「春泥の脅迫状」 は静子を怖がらせるための小山田氏のいたずらであり (小山田氏は変態性欲者であったことが明される)、そのいたずらが過ぎて事故死したのだという推理を組み立てる。この推理は糸崎検事あての意見書の草稿という体裁をとっており、それ自体、探偵の論理 (寒川の推理) と、それによって明される犯罪の論理 (小山田氏の犯罪遊戯) との具体的表現である。 また、この間の探偵の論理の流れの中には、探偵小説的サスペンスを盛り上げる巧みな叙述が点綴されている。
あるいはまた、
特に後者は、井上良夫もその叙述の技巧を賞賛して引用している箇所であり、読者を探偵の論理の展開過程に引きずり込まずにはおかない強烈なサスペンスを伴っている。 意見書の推理は非常に綿密に、説得力をもって組み立てられているのだが、それを提示するや否や、寒川は (つまり作者は) やがてこの推理がくつがえされることを暗示する。
このような暗示に富んだ叙述もまた、探偵小説的サスペンスを醸成するうえできわめて効果的な役割を果たしているといえよう。もっとも、この後量産されることになる通俗スリラー長篇にはこうした叙述法が多用され、文章に彫琢を欠くこともあって、それらはいささか鼻につくほどであるが。 意見書の推理は、天井裏に落ちていたボタンが手袋から取れたのが、天井の灰汁洗いよりも前であったという事実の発見によって破綻する。この事実の発見は静子犯人説を組み立てる契機となるもので、作品構成上蝶番にあたる重要な部分なのだが、いささか不自然であり、やや苦しい感じである。というのは、発見のきっかけとなるのが、
という部分なのだが、ここで 「変なことを口走」 る必然性というのが何もなく、作者の御都合主義ともとれるからである。しかし、これも今回論理展開に特に注意しながら読み直してみた結果初めて気がついたことであり、普通に読んでいけば作者の巧みな叙述に惑わされてそのまま読み過ごしてしまうだろう。小さな瑕瑾というべきである。 ともあれ、上の事実の発見によって、寒川は先の意見書の推理を放棄し、さらに大胆な説を立てることになる。この寒川の新しい推理は、古ぼけた化物屋敷のような家の土蔵の中で、静子を相手に語られる。先の意見書を書いた頃から、寒川と静子はその家で 「ただれきった悪夢のような」 逢引きを重ねるようになっていたのだ。寒川の推理は、大江春泥は小山田静子である、というものだった。静子が春泥と、その細君と、小山田夫人との一人三役をつとめていたというのである。ここに至って、静子の犯罪の論理と寒川の探偵の論理が、土蔵の中のただれきった愛欲を思わせるような姿で絡み合ったまま読者の前に提示され、クライマックスを迎える。翌日、静子は隅田川に身を投じて水死をとげるのである。 この後、最終節ではさらに上の解決に対する寒川の疑惑が記されているが、それは上の解決を否定して 「無解決」 に持ち込むほどの力はもっておらず、単に作品に余韻を与えるにとどまるものであろう。 以上見てきたように、「陰獣」 においては、その冒頭から結末に至るまでほとんどあらゆる箇所で犯罪の論理と探偵の論理の拮抗が見られ、両者が相まって形成する論理的興味が全篇を支配しているのである。ふり返って冒頭の一節を思い出すとき、読者は、書出しにおいてすでに、全篇を貫く二種類の論理の拮抗のモチーフがそれとなく提示されていたことに気づかずにはいられないだろう。
4 トリックその他 (1) トリック 探偵小説のトリックについては、様々な基準によって分類することが可能であるが、その主体と対象――誰が誰に対して用いるトリックか、という観点から、次のように二大別することもできるだろう。一つは、作中の犯人が、自分が犯人として疑われないように探偵役その他の作中人物に対して仕掛けるトリックで、密室、アリバイ等犯行の手段、方法に関するトリックはおおむねこのタイプに属する。 もう一つは、作者が読者に対して仕掛けるトリックである。『アクロイド殺し』 や 『オリエント急行の殺人』 におけるような 〈意外な犯人〉 のトリックは、エルキュール・ポアロに対してというよりも、むしろ直接読者を相手に仕組まれたトリックであるといえよう。構成に工夫をこらした 〈叙述トリック〉 といわれるものもこれに該当する。いま仮に前者のタイプのトリックを 「犯人のトリック」、後者のそれを 「作者のトリック」 と名づけておく。 もっとも、犯人のトリックといっても、犯人がそのトリックを使用するのは作者のたくらみによるのであり、結局のところ作者が犯人にそのトリックを使用させることによって読者の目をくらませ、謎解きゲームに勝利することを目的としているのである。その意味では、犯人のトリックも作者のトリックと区別できないかもしれないが、作者がそのトリックを直接使用するか、犯人を通じて間接的に使用するかによって、一応上のように分けてみたまでである。このような分類を行うことが、「陰獣」 のトリックを分析するうえで有効と考えられるからである。 「陰獣」 における犯人のトリックは、小山田静子の一人三役である。すなわち、静子が大江春泥であり、また、春泥の細君であったというのである。もっとも、このうち 「大江春泥」 については、その名前で小説を書いたほかは、浅草公園の浮浪人=道化服の男を利用しているのだから、実質的には 「春泥の細君」 との一人二役である。 井上良夫はこのトリックを、「充分興味深くはあるが、それだけにきわどいトリックであり、苦しい芸当である」 と評しているが、筆者には必ずしもそうは思われない。一人三役といっても、共犯者を利用しているのだから (その意味では二人四役)、自身は髪を結いかえ、目がねをかけ、メッキの金歯をはめる程度の簡単な変装によって 「春泥の細君」 を演じれば済んだのである。しかもその変装にもルパン式の早業が要求されるわけでもなく、充分の時間的余裕があったのだから、別段きわどさ、苦しさといったものは感じられない。充分成立可能なトリックだと思われる。トリックの成立可能性は、一面周囲の状況に大きく依存するものであるが、その点作者に手抜かりはなく、用意周到の設定がなされている。井上も 「トリックのあやふやさが、如何にもあやふやらしくなく扱いこなされている」 点は 「最上級の出来栄である」 として賞賛している。 乱歩が探偵小説のトリックのうち特に 「一人二役」 を好んだことは、既にしばしば指摘されている。『続・幻影城』 所収の 「類別トリック集成」 によれば、一人二役トリックはトリック例総計821中の130例を占め、最高の頻度を示しているが、乱歩の自作中における使用頻度は (統計を試みたわけではないが) それよりはるかに高い割合を示すであろう。技巧的制約がゆるやかな通俗長篇においては特にその傾向が顕著で、いささかうんざりさせられるほどである。この偏好を乱歩の性格の二面性から説明する考え方もあるが、より直截に 「変身願望」 に基づくものと見てよいのではないか。自分以外のものに化けるということの魅力が、椅子や、百科事典 (少年もの) に化ける物語さえ生んだのである。 「陰獣」 のトリックを特徴づけるものは、しかし、この常套的な犯人のトリックではない。作者自身を――その分身ともいうべき大江春泥の姿を借りて――作中に登場せしめた大胆な趣向が、この作品における最大の目くらましとなっているのである。 実際、大江春泥に関する部分の記述は、多く作者自身を彷彿とさせずにはおかない。その経歴、作風、個々の作品名―― 「屋根裏の遊戯」 「一枚の切手」 「B坂の殺人」 「パノラマ国」 「一人二役」 「一銭銅貨」 ……。さらに、「彼は一年ばかり前から、ぱったり小説を書かなくなり、所在をさえくらましてしまった」 ――作者自身の休筆をも抜かりなく書き込んであるのには、苦笑せざるをえない (「陰獣」 は十四カ月の休筆の後はじめて執筆された)。筆者などは 『探偵小説四十年』 によって後からその間の事情を承知したのだが、当時の読者に対しては一層大きな目くらましの効果をあげたことだろう。大江春泥の実在性は、実に作者自身の存在によって担保されたのである。 しかし、この作者のトリックは、作者が意識的に用いたものではなかったようである。『探偵小説四十年』 において作者は、甲賀三郎の 「一読した時には、本名平田一郎、筆名大江春泥という男に、よく似ている実在の人間 (即ち江戸川乱歩) を知っているために、つい大江春泥の実在性を疑わなかった……」 という文章を引用し、
と述べている。作者が必ずしも作品のすべてを知り尽くしているわけではないという一例になろうか。作者自身は 『探偵小説四十年』 の同じ箇所で 「作品のそとまで溢れ出したトリック」 という言い方をしている。 しかし、この 「陰獣」 におけるトリックの場合、これが作者のトリックとして成立するかどうかは、作者の意識とは無関係に、もっぱら読者の側の事情によって左右されることになるだろう。このトリックが最も効果を上げたのは、この作品が発表された当時の 「新青年」 の読者――大正12年に 「二銭銅貨」 によって登場して以来の乱歩の作家的経歴を承知している人々に対してであったろう。一方、「陰獣」 によって初めて乱歩作品に接する読者を想定してみれば、彼にとってはこの作者のトリックはまるで意味をもたないはずである。つまり、作者自身を利用したこのトリックは、当然のことながら作者に関する知識を前提としているのであり、作者とその作品について予備知識をもたない読者にに対しては、トリックとして成立しないのである。 ここに、このトリックの類例のない特異性とともに、大きな弱点があるわけである。現時点における 「陰獣」 の評価が戦前より低下しているように見えるのは、戦後すぐれた作品が数多く発表されたことにもよるが、一つには、読者層の交代によって、この作品の最大のトリックがトリックとして成立しなくなったという事情も考えられるのではなかろうか。 (2) その他の趣向について トリック以外の趣向について若干ふれるならば、まず注意をひかれるのは、最終節において結末をあいまいにしている点である。前節で寒川から大江春泥の正体についての推理を突きつけられて、静子は自殺する。しかし、やがて寒川の胸には恐ろしい疑惑が頭をもたげてきたのである。静子は犯人ではなかったのではないか。大江春泥は実在するのではないか。――この、一度つけた結末をさらにくつがえす手法も多くの作品で用いられており、一人二役のトリックとともに乱歩作品を特徴づけている。 しかし、「陰獣」 のこの趣向に対しては非難が多かったようである。平林初之輔は
と述べており (「『陰獣』 その他」)、他の多くの評者も同意見だったようである。しかし、筆者は格別不快を感じることはなかったし、純粋に技巧的に見ても特に非難されるべき欠点とは考えられない。 先にもふれたように、最終節の疑惑はあくまで疑惑にとどまるのであって、前節において提示された静子犯人説をくつがえすだけの力はもっていない。疑惑が弱いというよりは、前節の推理が非常に緻密で説得的であるため、多少の疑惑によっては容易に結論の座を追われないのである。そうとすればこの部分はあっても意味がなく、不要であるともいえるが、あって邪魔になるという性格のものではあるまいと思う。というより、犯人が正体を発かれて自殺し、それで終ってしまうのでは何かしらあっけない感じもあるので、作品に余韻を与える意味で、最終節はこのまま置かれてよいと考える。 その他、この作品で印象に残るのは、随所で感じられるサスペンスである。このうち論理的サスペンスは、井上良夫の指摘するように構成と叙述の妙から生じるものであるが、他に扱われている素材自体から感じられるサスペンスもあり、この魅力も捨てがたい。 たとえば、博文館の記者本田の語る大江春泥についての話。春泥が浅草公園でとんがり帽と道化服をつけて立っていた、という報告にギョッとさせられるのは寒川だけではあるまい。あるいは、天井裏からかすかに聞こえてくる時計の音――闇の中で息を殺している陰獣 (井上良夫は、こうした部分に感じるサスペンスは後になってすべて静子の作り話であったとわかるので興醒めであると書いているが、たとえウソであったとしても、筆者にはそのウソ自体が面白い。作り話といえば、作品全体が作り話なのだ)。あるいは、汽船発着所の便所の下に、浮いては沈みしていた死体の顔。あるいはまた、寒川が前に座っている自動車の運転手が大江春泥ではないかという妄想を抱く場面、等々。これらのディテールから感じられる強烈なサスペンスが、「陰獣」 にありきたりの本格ものでは味わえない魅力を与えていることもまた否定できない事実である。
5 結語に代えて 前節までを書き終えてから、しばらくの時間が経過した。 構成上 「緒論」 と対応させる意味で 「結語」 の標題を記してはみたものの、言うべきことは本文中で言い尽くしており、ここにあらためて書くことは何もないように思われたのである。 しかし、時間を隔ててふり返ってみると、本文に述べたことが妥当であったかどうか、枝葉末節にこだわり肝心の事柄には少しもふれない見当違いの議論ではなかったのか、といった疑いが兆し始めているのを感じる。はたして自分は 「陰獣」 を読んだといえるのだろうか。 たとえば、論理的興味の分析の場面に限ってみても、犯罪の論理と探偵の論理の拮抗という把握自体、的確なものであったかどうか。両者は表面上拮抗しているように見えても、それはあくまで一方の優位を前提として演じられたお芝居ではなかったのか。このことを考えるとき思い出すのは、チェスタトンのブラウン神父譚の一篇でパリ警視庁の名探偵がもらした自嘲の言である――犯罪者は独創的な芸術家だが、探偵というのはその批評家にすぎない。同じような関係が犯罪の論理と探偵の論理の間にも見られるのではないか。犯罪の論理の優位。探偵の論理は、つまるところ犯罪の論理を紹介する幕引きの役割をつとめるにすぎない。そういえば、乱歩も繰り返し書いていたではないか。探偵小説の骨は、恐ろしい、風変わりな犯罪の創造にあると。 さらにいえば、探偵小説は論理とトリックのみ論ずればそれで事足りるものなのか。論理の光明は鮮やかに輝くけれども、その背後には巨大な闇がある。論理では到底明し尽くすことのできない、暗い、深い、闇。探偵小説の魅力は、より深くこのような闇によって支えられていたのではないか。…… 日を経るにつれて、論理の光明は薄らいでゆき、闇が私を侵し始める。ちょうど、論理による告発が静子を死に追いやった後で、寒川の前にふたたび大江春泥の幻影が立ち現れてきたように。 ※ 引用のテキストとしては、『江戸川乱歩全集』 (昭53〜54、講談社) 及び中島河太郎編 『江戸川乱歩――評論と研究』 (昭55、講談社) を使用した。
(2005.11.16掲載)
|